拡大
「電卓技術教科書〈基礎編〉(1971年)」B6版、356ページ
「電卓技術教科書〈研究編〉(1973年)」B6版、334ページ
本書を入手した経緯
本書のことは1年前に「電卓を作りたいという妄想」という記事で触れていた。この記事の中で僕は次のように書いている。
「たとえ100円ショップで売られるようになろうとも、電卓が電卓であるかぎり論理回路が簡単になるわけではない。自作するのは無理だとしても、せめて四則演算の電卓でよいから回路を全部理解してみたい。どうして電卓ごときにあれだけの電子部品が必要なのか、僕にはさっぱり理解できていないのが悔しい。」
「理数系を標榜するのであれば電卓の回路くらいは「一般常識」としておさえておきたいものだ。人生の目標がまたひとつ増えた。」
本書はこの目標を実現するためにはベストな本で、1969年に発売されたCompet CS-12Dをはじめ、その後に発売された電卓について高校生レベルの基礎から解説した教科書だ。この電卓の製造元のシャープ(株)が監修している。
SHARPCompet CS-12D (1969)
![]()
監修者は1971年当時のシャープ(株)代表取締役専務・産業機器事業本部長(現在同社顧問)の佐々木正氏だ。本書刊行当時は56歳、現在98歳になられている。本文の各章は同社の技術者が分担して執筆した。
だから先週アマゾンで中古本を見つけたときは本当に驚いた。公共図書館や大学の図書館には置いてあるものの、中古市場ではほとんど流通しておらず僕は入手するのをあきらめていた。(いや、「だめもと」でときどき検索していたのだからあきらめていなかった。)今度お目にかかるのはいつになるかわからないから、ためらいなく注文ボタンをクリックしたわけだ。
本書の詳細
本の詳細は、詳細な目次も含めて次のページで事細かく説明されている。
電卓技術教科書
http://www.protom.org/mad/0069.htm
「基礎編」では1969年に発売されたCompet CS-12Dの実際の論理回路を例に取り上げながら四則演算電卓のしくみが詳しく解説される。そして巻末には全回路図が掲載されているのだ。この機種は前回の記事で紹介したCompet CS-12Aとほとんど同じ製品だ。発売時期も3ヶ月しか違わない。半年も前に手に入れたたCompet CS-12Aのことを一昨日のタイミングで「IC電卓ノスタルジア (SHARP Compet CS-12A, 1969年)」として紹介したのは本書を入手できたことがきっかけだった。「研究編」では関数電卓で必要な超越関数(三角関数や指数・対数関数)を計算するためやプログラム機能のための論理回路も解説されている。
「基礎編」の章立て
序章:電卓の歴史と将来の展望
第1章:電卓とは
第2章:電卓の基礎理論
第3章:電卓の実際
第4章:入・出力装置
第5章:演算装置と演算制御
第6章:演算方式
第7章:電源回路
第8章:電卓の操作方法
巻末:
1.コンペットCS-12Dの全回路図
2.わが国の電卓の一覧表
「研究編」の章立て
第1章:電卓の高級化
第2章:新しい電卓
第3章:集積回路
第4章:電卓の製品設計
第5章:電卓の安全規格
第6章:電卓の信頼性
第7章:電卓の製造・検査工程
第8章:ユーザーとの諸問題
電卓とはどういうものか
電卓が電卓として動作するためには、その内部に「制御回路」が必要になる。キーが押されるたびにどのような処理をすべきかは押されるキーによって違ってくる。
たとえば「1」、「2」、「3」、「.」、「5」という入力に対して「123.5」という10進数の小数を一時記憶しなければならない。「5」を押した時点では、まだ次に他の数字が押されるかもしれない。どのタイミングでどのようにこの小数をレジスタに格納したらよいだろうか?そのようなキーシーケンスによる状態遷移を処理するのは「制御回路」の役割だ。
また入出力回路もある。キー入力は1つのスイッチがオンになるだけだから、これを2進数に変換しなければならない。この2進数は数字出力のために蛍光表示管の規格に合った信号に変換する回路も必要だ。(エンコーダ回路とデコーダ回路のこと。)
そしてもちろん演算回路も必要だ。加減乗除は2進数で行うが、どのようなアルゴリズムで行えばよいのだろう。整数だけでなく正負の小数の加減乗除である。乗算と除算のアルゴリズムは特に難しい。電子工学科の大学院レベルの内容だ。学部レベルだとせいぜい「簡単な電卓の設計」というページで解説されているような自然数1桁の足し算電卓くらいまでしか学ばないのだ。
参考ページ:
「加減乗除と小数の計算手順を理解したい。」
ウィキペディアの記事:乗算器、除算器)
60年代の電卓はこのようなことを「ワイヤードロジック(結線論理)」で実現していた。トランジスタやダイオードなど(60年代後半にはICも含まれる)を配線して論理回路を構成していたのである。ただし本書の基礎編を読むとCompet CS-12Dは「ワイヤードロジック」を採用してはいるものの、制御回路の部分は「マイクロプログラム論理」で作られている。説明がややこしいが、一部の回路は「コンピュータ的」なのだ。
その点「マイクロコンピュータの誕生―わが青春の4004:嶋正利」で触れたビジコン社の電卓は60年代後半「マイクロプログラム論理」で設計されたLSI電卓で、その後Intel 4004という世界初のCPUを内蔵した電卓(『Busicom 141-PF』)として発売された。シャープやカシオの電卓はCPU電卓ではない。
本書が出版されたのは1970年代はじめである。電卓の開発競争が激化していた時代にもかかわらずこのように社内機密的な技術情報をよくも市販したものだと思ったのだが、今とは事情が違っていることに気がついた。
60年代当時、電卓をはじめ電子製品や電気製品を買うと、説明書にはその製品の回路図が添えられているのが普通だった。電気製品はまだ高価だったので故障しても今のように簡単に買い替えられるわけではない。街の電気屋さんに修理してもらうのが一般的だった。そのときに修理担当者が頼りにしたのが製品に付属していた回路図なのだ。ヤフオクを「回路図」というキーワードで検索してみると当時の電気製品の電子回路図が(そして、なんと自動車の電子回路図までもが)高値で取引されていることがわかる。
だから本書が市販されても開発競争の足を引っ張ることはなく、学生や技術者向けの教科書として大いに役立ったのだ。
電卓について学ぶ方法
ところで電卓のしくみを学ぶために当時の教科書を入手しようとしても難しいことがわかる。
たとえばヤフオクで「電子計算機入門」というキーワードで検索してみるとコンピュータ入門系の本ばかりヒットしてしまう。そのような本の前半では2進数やANDやORなどの論理ゲート回路、そのハードウェアの解説が書かれているがコンピュータを前提とした解説で「電卓用」ではない。後半はアセンブリ言語やFORTRANなどプログラミング言語の話題になってしまう。これは当時、コンピュータは「電子計算機」と呼ばれるのが普通だったからだ。(そういえば、先日打ち上げが中止された「イプシロン」ロケットについて、プロジェクト・リーダーの会見でも「コンピュータ」ではなく「計算機」という言葉が使われていた。)
このようなわけで本書は現在では「幻の技術解説書」であり、そして70年代当時においては電卓のしくみを開発者と同じレベルで学ぶことのできる貴重な本だったのだ。
「基礎編」の6ページには1964年から1971年にかけて発売されたシャープ(60年代は早川電機工業)の電卓一覧表がある。Compet CS-12Aの発売年月がわかったのもこの表のおかげだ。
シャープ電卓一覧表(クリックで拡大)
![]()
シャープのデスクトップ電卓の歴史
http://www.dentaku-museum.com/calc/calc/1-sharp/1-sharpd/sharpd.html
ところで本書に頼らず、現代の方法で電卓のしくみを学ぶことも可能だ。これについては「加減乗除と小数の計算手順を理解したい。」という記事で詳しく紹介している。加減乗除だけでなく、関数電卓の論理回路まで学ぶことができる。
本書を入手できて僕はとても満足して幸せな気持ちになっているのだが、本は読まなければただの紙だ。いずれ両方とも読んで、それぞれレビュー記事を書きたいと思う。本書を入手して以来、1960年代電卓開発にたずさわった技術者と知り合いになりたいという気持ちがふつふつと沸いてきた。そのような方々は今では70代、80代になっていることだろう。もちろんお知り合いになるのは本書を読み終えてからのほうがよいと思う。
本書に関心がある方のために
本書がアマゾンに出品されることはほとんどないのだが、たとえ時間がかかってもいいから入手したいという方のためにリンク・ページを設けておこう。
「電卓技術教科書〈基礎編〉(1971年)」
「電卓技術教科書〈研究編〉(1973年)」
![]()
![]()
なお〈研究編〉は後に増補版が刊行されている。
「電卓技術教科書〈研究編〉(1976年)」
とりあえず実物を見てみたいという方は次のリンクから検索してみてほしい。日本各地に「保管」されていることがわかる。(おそらく「閉架」にしまってあるのだろう。)
国立国会図書館サーチ(公共図書館)で「電卓技術教科書」を:検索してみる
全国の学校図書館で「電卓技術教科書」の検索をしてみる:
「〈基礎編〉(1971年)と〈研究編〉(1973年)」、「〈研究編〉(1976年)」
ヤフオクで「電卓技術教科書」を:検索してみる
関連記事:
IC電卓ノスタルジア (SHARP Compet CS-12A, 1969年)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/9fead04c16784b42226ea8f280dc32a7
電卓を作りたいという妄想
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/01cf6bc6669bf0956a792bce292f97f1
加減乗除と小数の計算手順を理解したい。
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/44687dc879c9a6642b59c49a0c7cc3b3
算数チャチャチャ(NHKみんなのうた)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/5f45451ee92873728f3046ed36cdce71
応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。
![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()
![人気ブログランキングへ]()
![]()
![]()
いつもだとここに詳細目次を書くのだが、「電卓技術教科書」に書かれているのでそちらを見てほしい。
そのかわりにこちらの記事では「基礎編」、「研究編」の冒頭部分、監修者の佐々木正氏による「はしがき」をそれぞれ紹介しておこう。
「基礎編」に書かれている「はしがき」
電子式卓上計算機(電卓と略称される)は、多くの意味において特筆すべき製品の一つであります。最近の電子技術を応用した点においては電子計算機と変わりなく、すなわち小規模ながら記憶・演算・制御・入出力の各装置を有し、四則計算(加減乗除)を中心にして各種の事務・技術計算を簡単な操作で行なわせるようにした計算装置であります。
電子計算機が高度の有機的機能をもつ情報処理装置へ発展したのに対し、電卓は事務所・家庭をと言わず、大衆に、より身近かな実用性ある製品として発展したのが特徴です。電卓には四則演算を主にした電子ソロバンから、複雑な各種の計算ができるプログラマブルな高級機種にいたるまで、非常に広範囲にわたっております。さらに最近は電卓を核とした応用機器が開発されはじめ、あらゆる部門に電卓技術が浸透しつつある状態です。
一方電卓に使用されている素子の面から考えましても、過去において日本のトランジスタ産業がラジオ・テレビにより大きな発展を遂げたごとく、現在の集積回路(IC)および大規模集積回路(LSI)産業の発展は電卓に負うところが非常に大きいことです。これらの点を考えますと、電卓は小形ではありますが最新の電子技術の粋を集めたものであり、ごく最近まで一般大衆には無縁と考えられていた宇宙技術で開発されたLSI等が、かくもすみやかに地上で一般の誰もが手のとどく範囲に引寄せられたことは、驚くべきことであります。
このように普及してきた電卓について系統的にまとめられた本が見当たらず、断片的なものにかぎられ、その刊行が強く要望されるようになってまいりました。本書はこれらの要望に答えるために、電卓全般を網羅した系統的な刊行物としてまとめたものであります。
内容は電卓の使用者に参考になるように、サービス技術より見て書かれたもので、高校・大学初級の人々を対象にして記述してありますが、一般の利用者も考慮し、わかりやすく解説してあります。使用の便宜を考慮して上下2巻に分かち構成することとしました。上巻では一般の電卓についての基礎的事項より説明を始め、代表的機種としてシャープ電卓(CS-12D)を例にとって具体的に説明しました。下巻にはこれらの基礎に立って、さらに高級機種およびLSI化機種について深くかつ広範囲な説明を加えることにしました。
本書はその上巻:基礎編として刊行されたもので8章から構成されています。第1章には緒論として電卓の一般概念を、第2章には電卓に使用されている回路の基礎となっている論理数学、論理素子、論理回路について説明を加え、第3、4、5、7章は電卓の操作方法、ハードウェア的解説を一般的構成、入出力装置と記憶装置、演算制御と装置、電源回路と順に説明し、第6章にはそのまとめとして具体的な演算方法を取り上げてあります。また第8章には電卓取扱上の注意、およびその他の機種の操作方法につき述べて参考に提供してあります。
「研究編」に書かれている「はしがき」
先般“基礎編”を出版したのは昭和46年の夏ごろでしったが、その後電卓は成長産業として、その機能・技術において格段の進歩を示し、その研究から販売にいたる広範囲にわたって、種々の革新がなされてきました。
昭和45年(1970)においては、全世界の機械式・電気式および電子式の卓上計算機の需要は580万台で、そのうち電卓は162万台と28%を占め、日本は全電卓生産量の80%にあたる130万台を生産していましたが、翌昭和46年(1971)には全卓上計算機の需要は630万台、そのうち電卓は250万台を占め、日本はこのうち210万台と、世界の全電卓生産量の84%を生産しました。さらに昭和47年(1972)については、全世界の集計は終っていませんが、日本の総生産量は400万台を越していると思われています。
とくに昭和47年中には、CONSUMER-個人用電卓の市場と事務機用電卓のし上が明確に分離を始めました。上の400万台の生産の中で、CONSUMER-個人用電卓は260万台と見られ、実に60%を占めるにいたりました。
このように普及発展してきた電卓の技術の中で、特にLSIは、昭和45年ごろには、8桁を標準にとって説明すると、LSI 4チップと周辺部品で構成していましたが、昭和46年には1チップに納める集積化技術が成功し、47年にはさらにその集積化を高めることにより周辺部品点数を減らし、また表示管の低価格化、キー・ボードの簡易化によって材料構成費の減少をうながし、さらには1チップによる工数減少による原価切下げに成功しました。そして日米両国とも、低価格・個人用のマーケットを米国において創出し、ELECTRONICS誌をして、1973年はCONSUMER MARKET(パーソナル)は9,000万ドル市場、事務用MARKETは4億6,300万ドル市場といわせる状態となりました。
一方この事務用電卓も、LSI内のシステムにROM、RAM方式が採用され、さらにPLA、RPS (parallel processing system)の方式が開発されるにおよんで、高級電卓も低価格化普及を呼び、少なくとも1976年までは急成長する産業だといわれるにいたりました。
この両マーケットを支持するLSI、表示装置、キー・ボード、印字機構について、それぞれのマーケットに適応する技術の進歩が1チップになっても急速に行なわれており、つぎにいかなる技術革新が出現するか予断を許さない状況にあります。
LSIにおいては、上記のようなシステムの開発のほか、その構造・原理においても、従来のP-MOSに対し電池の寿命を長くするためにC-MOSの技術も開発され、さらに新しい構造の研究が行なわれています。表示装置では、従来のニキシー、蛍光表示管は、一方は構造的に多文字化され平板化され、他方LEDが実用化の緒につき、さらにはあらたな原理のもの(たとえば液晶)の出現を目前にしています。
本書においては、第1章に印字・表示両電卓の機能およびシステムの高級化について解説し、また第2章においては新しい電卓に用いられているシステムおよび装置について説明し、電子ソロバン、事務用および科学技術用電卓をその応用例として取上げました。
第3章には、電卓に使用されているLSIについてその技術紹介を行ない、技術進歩の主体となっている点だけを記述しました。なお表示装置については第2章に述べられていますが、キー・ボードにも相当の進歩が見られており、これについても併記したかったのですが、まだ進歩の過程にあり、今回紹介することは早計と考え、次回に譲ることにしました。
第4章にはこれらの部品・装置を使用して電卓の製品設計を行なう場合の手順とその問題点について述べ、第5章には最近問題になりはじめている安全規格の問題、第6章には信頼性について試験方法および保証行為について説明しました。また第7章では以上にもとづいて製造を行なう場合の製造工程、検査工程について説明し、第8章では現在行なわれているサービスに関し、ユーザーとの問題点について紹介しました。
本稿は、だいたい1年前までの技術と問題点を紙数に能うかぎりの説明を行なったつもりですが、脱稿時、そのときの現状をみて物足りなさを感じていますが、説明の不十分な点は再度機会をみて補正させていただくとして、読者諸氏の御批判・御意見をできるだけおうかがいし、さらに追補する機会を得たいと思っております。
「電卓技術教科書〈基礎編〉(1971年)」B6版、356ページ
「電卓技術教科書〈研究編〉(1973年)」B6版、334ページ
本書を入手した経緯
本書のことは1年前に「電卓を作りたいという妄想」という記事で触れていた。この記事の中で僕は次のように書いている。
「たとえ100円ショップで売られるようになろうとも、電卓が電卓であるかぎり論理回路が簡単になるわけではない。自作するのは無理だとしても、せめて四則演算の電卓でよいから回路を全部理解してみたい。どうして電卓ごときにあれだけの電子部品が必要なのか、僕にはさっぱり理解できていないのが悔しい。」
「理数系を標榜するのであれば電卓の回路くらいは「一般常識」としておさえておきたいものだ。人生の目標がまたひとつ増えた。」
本書はこの目標を実現するためにはベストな本で、1969年に発売されたCompet CS-12Dをはじめ、その後に発売された電卓について高校生レベルの基礎から解説した教科書だ。この電卓の製造元のシャープ(株)が監修している。
SHARPCompet CS-12D (1969)

監修者は1971年当時のシャープ(株)代表取締役専務・産業機器事業本部長(現在同社顧問)の佐々木正氏だ。本書刊行当時は56歳、現在98歳になられている。本文の各章は同社の技術者が分担して執筆した。
だから先週アマゾンで中古本を見つけたときは本当に驚いた。公共図書館や大学の図書館には置いてあるものの、中古市場ではほとんど流通しておらず僕は入手するのをあきらめていた。(いや、「だめもと」でときどき検索していたのだからあきらめていなかった。)今度お目にかかるのはいつになるかわからないから、ためらいなく注文ボタンをクリックしたわけだ。
本書の詳細
本の詳細は、詳細な目次も含めて次のページで事細かく説明されている。
電卓技術教科書
http://www.protom.org/mad/0069.htm
「基礎編」では1969年に発売されたCompet CS-12Dの実際の論理回路を例に取り上げながら四則演算電卓のしくみが詳しく解説される。そして巻末には全回路図が掲載されているのだ。この機種は前回の記事で紹介したCompet CS-12Aとほとんど同じ製品だ。発売時期も3ヶ月しか違わない。半年も前に手に入れたたCompet CS-12Aのことを一昨日のタイミングで「IC電卓ノスタルジア (SHARP Compet CS-12A, 1969年)」として紹介したのは本書を入手できたことがきっかけだった。「研究編」では関数電卓で必要な超越関数(三角関数や指数・対数関数)を計算するためやプログラム機能のための論理回路も解説されている。
「基礎編」の章立て
序章:電卓の歴史と将来の展望
第1章:電卓とは
第2章:電卓の基礎理論
第3章:電卓の実際
第4章:入・出力装置
第5章:演算装置と演算制御
第6章:演算方式
第7章:電源回路
第8章:電卓の操作方法
巻末:
1.コンペットCS-12Dの全回路図
2.わが国の電卓の一覧表
「研究編」の章立て
第1章:電卓の高級化
第2章:新しい電卓
第3章:集積回路
第4章:電卓の製品設計
第5章:電卓の安全規格
第6章:電卓の信頼性
第7章:電卓の製造・検査工程
第8章:ユーザーとの諸問題
電卓とはどういうものか
電卓が電卓として動作するためには、その内部に「制御回路」が必要になる。キーが押されるたびにどのような処理をすべきかは押されるキーによって違ってくる。
たとえば「1」、「2」、「3」、「.」、「5」という入力に対して「123.5」という10進数の小数を一時記憶しなければならない。「5」を押した時点では、まだ次に他の数字が押されるかもしれない。どのタイミングでどのようにこの小数をレジスタに格納したらよいだろうか?そのようなキーシーケンスによる状態遷移を処理するのは「制御回路」の役割だ。
また入出力回路もある。キー入力は1つのスイッチがオンになるだけだから、これを2進数に変換しなければならない。この2進数は数字出力のために蛍光表示管の規格に合った信号に変換する回路も必要だ。(エンコーダ回路とデコーダ回路のこと。)
そしてもちろん演算回路も必要だ。加減乗除は2進数で行うが、どのようなアルゴリズムで行えばよいのだろう。整数だけでなく正負の小数の加減乗除である。乗算と除算のアルゴリズムは特に難しい。電子工学科の大学院レベルの内容だ。学部レベルだとせいぜい「簡単な電卓の設計」というページで解説されているような自然数1桁の足し算電卓くらいまでしか学ばないのだ。
参考ページ:
「加減乗除と小数の計算手順を理解したい。」
ウィキペディアの記事:乗算器、除算器)
60年代の電卓はこのようなことを「ワイヤードロジック(結線論理)」で実現していた。トランジスタやダイオードなど(60年代後半にはICも含まれる)を配線して論理回路を構成していたのである。ただし本書の基礎編を読むとCompet CS-12Dは「ワイヤードロジック」を採用してはいるものの、制御回路の部分は「マイクロプログラム論理」で作られている。説明がややこしいが、一部の回路は「コンピュータ的」なのだ。
その点「マイクロコンピュータの誕生―わが青春の4004:嶋正利」で触れたビジコン社の電卓は60年代後半「マイクロプログラム論理」で設計されたLSI電卓で、その後Intel 4004という世界初のCPUを内蔵した電卓(『Busicom 141-PF』)として発売された。シャープやカシオの電卓はCPU電卓ではない。
本書が出版されたのは1970年代はじめである。電卓の開発競争が激化していた時代にもかかわらずこのように社内機密的な技術情報をよくも市販したものだと思ったのだが、今とは事情が違っていることに気がついた。
60年代当時、電卓をはじめ電子製品や電気製品を買うと、説明書にはその製品の回路図が添えられているのが普通だった。電気製品はまだ高価だったので故障しても今のように簡単に買い替えられるわけではない。街の電気屋さんに修理してもらうのが一般的だった。そのときに修理担当者が頼りにしたのが製品に付属していた回路図なのだ。ヤフオクを「回路図」というキーワードで検索してみると当時の電気製品の電子回路図が(そして、なんと自動車の電子回路図までもが)高値で取引されていることがわかる。
だから本書が市販されても開発競争の足を引っ張ることはなく、学生や技術者向けの教科書として大いに役立ったのだ。
電卓について学ぶ方法
ところで電卓のしくみを学ぶために当時の教科書を入手しようとしても難しいことがわかる。
たとえばヤフオクで「電子計算機入門」というキーワードで検索してみるとコンピュータ入門系の本ばかりヒットしてしまう。そのような本の前半では2進数やANDやORなどの論理ゲート回路、そのハードウェアの解説が書かれているがコンピュータを前提とした解説で「電卓用」ではない。後半はアセンブリ言語やFORTRANなどプログラミング言語の話題になってしまう。これは当時、コンピュータは「電子計算機」と呼ばれるのが普通だったからだ。(そういえば、先日打ち上げが中止された「イプシロン」ロケットについて、プロジェクト・リーダーの会見でも「コンピュータ」ではなく「計算機」という言葉が使われていた。)
このようなわけで本書は現在では「幻の技術解説書」であり、そして70年代当時においては電卓のしくみを開発者と同じレベルで学ぶことのできる貴重な本だったのだ。
「基礎編」の6ページには1964年から1971年にかけて発売されたシャープ(60年代は早川電機工業)の電卓一覧表がある。Compet CS-12Aの発売年月がわかったのもこの表のおかげだ。
シャープ電卓一覧表(クリックで拡大)

シャープのデスクトップ電卓の歴史
http://www.dentaku-museum.com/calc/calc/1-sharp/1-sharpd/sharpd.html
ところで本書に頼らず、現代の方法で電卓のしくみを学ぶことも可能だ。これについては「加減乗除と小数の計算手順を理解したい。」という記事で詳しく紹介している。加減乗除だけでなく、関数電卓の論理回路まで学ぶことができる。
本書を入手できて僕はとても満足して幸せな気持ちになっているのだが、本は読まなければただの紙だ。いずれ両方とも読んで、それぞれレビュー記事を書きたいと思う。本書を入手して以来、1960年代電卓開発にたずさわった技術者と知り合いになりたいという気持ちがふつふつと沸いてきた。そのような方々は今では70代、80代になっていることだろう。もちろんお知り合いになるのは本書を読み終えてからのほうがよいと思う。
本書に関心がある方のために
本書がアマゾンに出品されることはほとんどないのだが、たとえ時間がかかってもいいから入手したいという方のためにリンク・ページを設けておこう。
「電卓技術教科書〈基礎編〉(1971年)」
「電卓技術教科書〈研究編〉(1973年)」
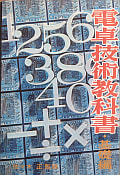

なお〈研究編〉は後に増補版が刊行されている。
「電卓技術教科書〈研究編〉(1976年)」
とりあえず実物を見てみたいという方は次のリンクから検索してみてほしい。日本各地に「保管」されていることがわかる。(おそらく「閉架」にしまってあるのだろう。)
国立国会図書館サーチ(公共図書館)で「電卓技術教科書」を:検索してみる
全国の学校図書館で「電卓技術教科書」の検索をしてみる:
「〈基礎編〉(1971年)と〈研究編〉(1973年)」、「〈研究編〉(1976年)」
ヤフオクで「電卓技術教科書」を:検索してみる
関連記事:
IC電卓ノスタルジア (SHARP Compet CS-12A, 1969年)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/9fead04c16784b42226ea8f280dc32a7
電卓を作りたいという妄想
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/01cf6bc6669bf0956a792bce292f97f1
加減乗除と小数の計算手順を理解したい。
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/44687dc879c9a6642b59c49a0c7cc3b3
算数チャチャチャ(NHKみんなのうた)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/5f45451ee92873728f3046ed36cdce71
応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。




いつもだとここに詳細目次を書くのだが、「電卓技術教科書」に書かれているのでそちらを見てほしい。
そのかわりにこちらの記事では「基礎編」、「研究編」の冒頭部分、監修者の佐々木正氏による「はしがき」をそれぞれ紹介しておこう。
「基礎編」に書かれている「はしがき」
電子式卓上計算機(電卓と略称される)は、多くの意味において特筆すべき製品の一つであります。最近の電子技術を応用した点においては電子計算機と変わりなく、すなわち小規模ながら記憶・演算・制御・入出力の各装置を有し、四則計算(加減乗除)を中心にして各種の事務・技術計算を簡単な操作で行なわせるようにした計算装置であります。
電子計算機が高度の有機的機能をもつ情報処理装置へ発展したのに対し、電卓は事務所・家庭をと言わず、大衆に、より身近かな実用性ある製品として発展したのが特徴です。電卓には四則演算を主にした電子ソロバンから、複雑な各種の計算ができるプログラマブルな高級機種にいたるまで、非常に広範囲にわたっております。さらに最近は電卓を核とした応用機器が開発されはじめ、あらゆる部門に電卓技術が浸透しつつある状態です。
一方電卓に使用されている素子の面から考えましても、過去において日本のトランジスタ産業がラジオ・テレビにより大きな発展を遂げたごとく、現在の集積回路(IC)および大規模集積回路(LSI)産業の発展は電卓に負うところが非常に大きいことです。これらの点を考えますと、電卓は小形ではありますが最新の電子技術の粋を集めたものであり、ごく最近まで一般大衆には無縁と考えられていた宇宙技術で開発されたLSI等が、かくもすみやかに地上で一般の誰もが手のとどく範囲に引寄せられたことは、驚くべきことであります。
このように普及してきた電卓について系統的にまとめられた本が見当たらず、断片的なものにかぎられ、その刊行が強く要望されるようになってまいりました。本書はこれらの要望に答えるために、電卓全般を網羅した系統的な刊行物としてまとめたものであります。
内容は電卓の使用者に参考になるように、サービス技術より見て書かれたもので、高校・大学初級の人々を対象にして記述してありますが、一般の利用者も考慮し、わかりやすく解説してあります。使用の便宜を考慮して上下2巻に分かち構成することとしました。上巻では一般の電卓についての基礎的事項より説明を始め、代表的機種としてシャープ電卓(CS-12D)を例にとって具体的に説明しました。下巻にはこれらの基礎に立って、さらに高級機種およびLSI化機種について深くかつ広範囲な説明を加えることにしました。
本書はその上巻:基礎編として刊行されたもので8章から構成されています。第1章には緒論として電卓の一般概念を、第2章には電卓に使用されている回路の基礎となっている論理数学、論理素子、論理回路について説明を加え、第3、4、5、7章は電卓の操作方法、ハードウェア的解説を一般的構成、入出力装置と記憶装置、演算制御と装置、電源回路と順に説明し、第6章にはそのまとめとして具体的な演算方法を取り上げてあります。また第8章には電卓取扱上の注意、およびその他の機種の操作方法につき述べて参考に提供してあります。
「研究編」に書かれている「はしがき」
先般“基礎編”を出版したのは昭和46年の夏ごろでしったが、その後電卓は成長産業として、その機能・技術において格段の進歩を示し、その研究から販売にいたる広範囲にわたって、種々の革新がなされてきました。
昭和45年(1970)においては、全世界の機械式・電気式および電子式の卓上計算機の需要は580万台で、そのうち電卓は162万台と28%を占め、日本は全電卓生産量の80%にあたる130万台を生産していましたが、翌昭和46年(1971)には全卓上計算機の需要は630万台、そのうち電卓は250万台を占め、日本はこのうち210万台と、世界の全電卓生産量の84%を生産しました。さらに昭和47年(1972)については、全世界の集計は終っていませんが、日本の総生産量は400万台を越していると思われています。
とくに昭和47年中には、CONSUMER-個人用電卓の市場と事務機用電卓のし上が明確に分離を始めました。上の400万台の生産の中で、CONSUMER-個人用電卓は260万台と見られ、実に60%を占めるにいたりました。
このように普及発展してきた電卓の技術の中で、特にLSIは、昭和45年ごろには、8桁を標準にとって説明すると、LSI 4チップと周辺部品で構成していましたが、昭和46年には1チップに納める集積化技術が成功し、47年にはさらにその集積化を高めることにより周辺部品点数を減らし、また表示管の低価格化、キー・ボードの簡易化によって材料構成費の減少をうながし、さらには1チップによる工数減少による原価切下げに成功しました。そして日米両国とも、低価格・個人用のマーケットを米国において創出し、ELECTRONICS誌をして、1973年はCONSUMER MARKET(パーソナル)は9,000万ドル市場、事務用MARKETは4億6,300万ドル市場といわせる状態となりました。
一方この事務用電卓も、LSI内のシステムにROM、RAM方式が採用され、さらにPLA、RPS (parallel processing system)の方式が開発されるにおよんで、高級電卓も低価格化普及を呼び、少なくとも1976年までは急成長する産業だといわれるにいたりました。
この両マーケットを支持するLSI、表示装置、キー・ボード、印字機構について、それぞれのマーケットに適応する技術の進歩が1チップになっても急速に行なわれており、つぎにいかなる技術革新が出現するか予断を許さない状況にあります。
LSIにおいては、上記のようなシステムの開発のほか、その構造・原理においても、従来のP-MOSに対し電池の寿命を長くするためにC-MOSの技術も開発され、さらに新しい構造の研究が行なわれています。表示装置では、従来のニキシー、蛍光表示管は、一方は構造的に多文字化され平板化され、他方LEDが実用化の緒につき、さらにはあらたな原理のもの(たとえば液晶)の出現を目前にしています。
本書においては、第1章に印字・表示両電卓の機能およびシステムの高級化について解説し、また第2章においては新しい電卓に用いられているシステムおよび装置について説明し、電子ソロバン、事務用および科学技術用電卓をその応用例として取上げました。
第3章には、電卓に使用されているLSIについてその技術紹介を行ない、技術進歩の主体となっている点だけを記述しました。なお表示装置については第2章に述べられていますが、キー・ボードにも相当の進歩が見られており、これについても併記したかったのですが、まだ進歩の過程にあり、今回紹介することは早計と考え、次回に譲ることにしました。
第4章にはこれらの部品・装置を使用して電卓の製品設計を行なう場合の手順とその問題点について述べ、第5章には最近問題になりはじめている安全規格の問題、第6章には信頼性について試験方法および保証行為について説明しました。また第7章では以上にもとづいて製造を行なう場合の製造工程、検査工程について説明し、第8章では現在行なわれているサービスに関し、ユーザーとの問題点について紹介しました。
本稿は、だいたい1年前までの技術と問題点を紙数に能うかぎりの説明を行なったつもりですが、脱稿時、そのときの現状をみて物足りなさを感じていますが、説明の不十分な点は再度機会をみて補正させていただくとして、読者諸氏の御批判・御意見をできるだけおうかがいし、さらに追補する機会を得たいと思っております。