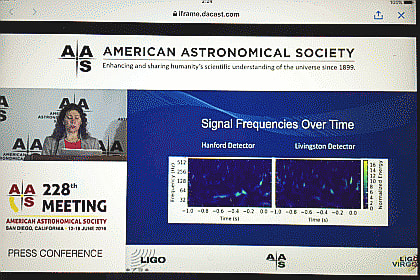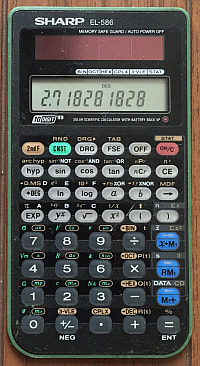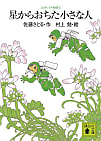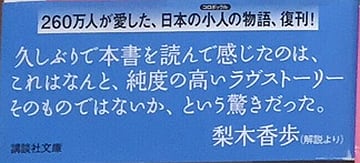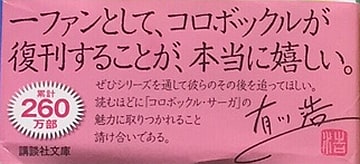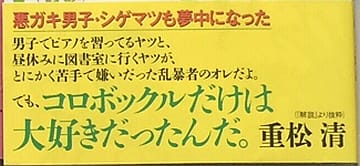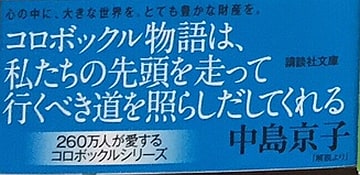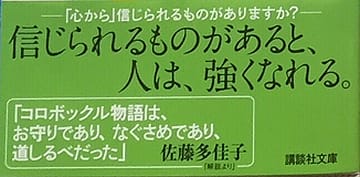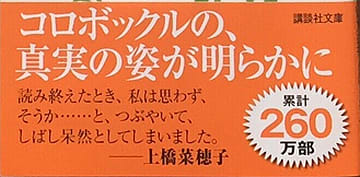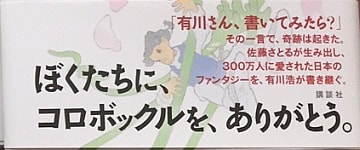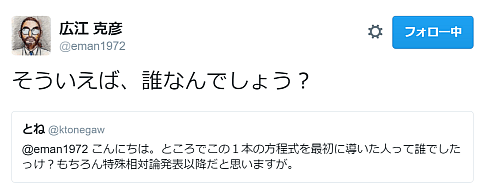「
人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの: 松尾豊」(
Kindle版)
内容紹介:
人類の希望か、あるいは大いなる危機なのか?「人間のように考えるコンピュータ」の実現へ、いま、劇的な進展が訪れようとしている。知能とは何か、人間とは何か。トップクラスの人工知能学者が語る、知的興奮に満ちた一冊。
2015年2月刊行、263ページ。
著者について:
松尾 豊(まつお ゆたか)
東京大学大学院工学系研究科准教授。1997年、東京大学工学部電子情報工学科卒業。2002年、同大学院博士課程修了。博士(工学)。同年より産業技術総合研究所研究員。2005年よりスタンフォード大学客員研究員。2007年より現職。シンガポール国立大学客員准教授。専門分野は、人工知能、ウェブマイニング、ビッグデータ分析。人工知能学会からは論文賞(2002年)、創立20周年記念事業賞(2006年)、現場イノベーション賞(2011年)、功労賞(2013年)の各賞を受賞。
理数系書籍のレビュー記事は本書で311冊目。
本書を読んだきっかけ
先日NHK EテレのサイエンスZEROで「
人工知能の大革命!?ディープラーニング」(
動画)が放送されたように、この数年人工知能関連のニュースをよく見かけるようになった。今日紹介する本の著者はこの番組で解説をされていた松尾豊先生だ。
チェスや将棋だけでなく囲碁でもコンピュータソフトが名人を打ち負かす時代になっている。数学パズルやボードゲームの世界だけですんでいるのなら、人工知能も安心して見ていられる。けれどもそうならないのは火を見るよりも明らかだ。ホーキング博士やビル・ゲイツが警告しているように人工知能は人類の存在を脅かすものになっていくのだろうか?
グーグルが進めている自動車の自動運転システムやソフトバンクのPepperなど、巨大企業がこの分野の研究を推し進めている。中国もこの分野では日本をしのぐ勢いで研究を進めているようだ。経済の面での国際競争力を維持するためには、国をあげて人工知能の研究と実用化を進めなければならないらしい。好むと好まざるとにかかわらず、確実に私たちはその恩恵と影響を受けることになる。
でも、そのように進むことは正しいのだろうか?心理的に受け入れられないこともきっとでてくるだろう。世の中には情報があふれている。人工知能と銘打っていても、単なる制御システムだったり、エキスパートシステムにすぎない製品もある。
人工知能をやみくもに恐れたり否定するのではなく、いま何がおきていて、これからどうなっていくのかを正しい知識を知ったうえで判断したい。それが本書のような人工知能についての入門書を読みたいと思った理由である。
僕にとっての人工知能
実をいうと僕は1980年代後半、大学4年になってからパソコン用日英・英日機械翻訳ソフトウェアを世界で初めて開発、販売したベンチャー企業でアルバイトをしていて、卒業後はそのままその会社(ブラビスインターナショナル株式会社、
参考ページ)に就職した。だから就職活動は経験していない。この会社は日英・英日だけでなく日韓・韓日の機械翻訳ソフトも開発してパッケージソフトとして販売していた。Windows 3.1はまだリリースされておらず、NEC PC-9800シリーズにインストールされたMS-DOS上で動作していた。
いずれにしてもこの時代の機械翻訳ソフトは文法の構文解析と用語辞書の品詞や付帯属性だけで翻訳するもので、意味論に基づいた処理は行われていない原始的なものである。時代を先取りしすぎていたためか、残念ながらビジネスとしては成功とまではいかず、その後この会社は解散してしまい、「
語彙機能文法(Lexical Functional Grammar)」に基づいて設計、開発をはじめていた第2世代の機械翻訳ソフトは陽の目を見ることがなかった。開発環境はDEC社の
VAX-11/780のC言語だった。(Amazonで語彙機能文法の解説書を
検索する。第2世代機械翻訳システム開発にかかわるエンジニアがバイブルとして読んでいた語彙機能文法の提唱者
Joan Bresnan(
Homepage)によるこの分厚い教科書が、いまではKindle版として発売されていることには隔世の感がある。)
大学での専攻が応用数学だったこともあり人工知能も僕の関心事のひとつで、当時は「
LISPで学ぶ認知心理学 全3巻」を読んでいた。当時、僕にはLISPの実行環境がなかったので理解は半分止まりであったが、おぼろげながらどこまで研究が進んでいるのかは理解していた。本書の中の言い方でいえば「第2次AIブーム」の最初の頃になるのだろう。この3冊を読んで僕は「人工知能が実現するのは当分先のことだな。」と安心していた。
ディープラーニングの衝撃
だからAlphaGoのニュースや
先日のサイエンスZEROを見たとき、昔とはくらべものにならないくらい発展したのだなと驚かされた。社会人になって最初に取り組んだ仕事が実を結ばなかったこともあり、機械翻訳や人工知能に対しては否定的な固定観念が身についてしまっていたからだろう。本書を読み終えた今でも、自分が生きているうちは人工知能も人類にとっての脅威とまでには成長しないだろうし、自然言語処理も人間の翻訳者の能力を超えることはないのではないだろうと思っている。
そもそも人間の思考や感情のしくみがニューロンを流れる電気信号のレベルで解明されているわけではないし、それはおそらく今後も無理なことだと思う。脳科学と基礎物理学は天と地、いや「宇宙の果てと地」くらい離れている。ディープラーニング(深層学習)が人間の脳のニューラルネットワークを模倣しているとはいえ、構造はまったく異なっているはずだ。しかし、そのようなモデルでさえAlphaGoや画像の認識技術として紹介されたように、人間が教えることなく「特徴検出」をみずから行い、学習していく能力をもっていることが、ディープラーニングが革新的で、注目を浴びている理由なのだ。
時間的制約のあるテレビ番組で紹介されるのは成功例だけである。それだけ見せられると一般視聴者は人工知能は万能だと思ってしがいがちだ。
先日のサイエンスZEROで紹介された人物を特定する画像認識にしても、文章を与えてその画像を「想像」させてディスプレイに移す例にしても、似た特徴をもった人がたくさんいたらどうなるか、あらかじめ学習させておく知識を膨大にしたとき正しいイメージを人工知能は想像できるのかなど、疑問点は残ってしまう。知識が膨大になればなるほど、対立する概念や矛盾が生じるのが現実の世界で起きることだからだ。だから、本書のように詳しく解説した本を読む必要がでてくる。
本書の概要
本書の章立ては次のとおりだ。
序章:広がる人工知能――人工知能は人類を滅ぼすか
第1章:人工知能とは何か――専門家と世間の認識のズレ
第2章:「推論」と「探索」の時代――第1次AIブーム
第3章:「知識」を入れると賢くなる――第2次AIブーム
第4章:「機械学習」の静かな広がり――第3次AIブーム(1)
第5章:静寂を破る「ディープラーニング」――第3次AIブーム(2)
第6章:人工知能は人間を超えるか――ディープラーニングの先にあるもの
終章:変わりゆく世界――産業・社会への影響と戦略
序章で現在私たちが直面している人工知能の紹介と人類への今後の影響を大まかに紹介する。次に第1章から第4章までは、段階を追って人工知能がどのように発展してきたかを詳細に解説する。そして第5章が現在ブームとなっているディープラーニングの解説だ。本書はすべて文系の方でも読めるように書かれているのでご心配なく。
そして第6章と終章では未来の予測だ。人工知能は人類を滅ぼしてしまう悪魔なのだろうか?軍事利用されたとき、それはどのような結果を生み出すのだろうか?そこまで遠い未来でなくても、今後産業や社会にどのような影響をおよぼしていくのだろうか?最初から最後まで興味の尽きない話題であふれている。
著者は人工知能研究の第一人者である。ご自身が夢をかけ、精力をつぎ込んできた世界なので、人工知能の可能性を信じているのはもちろんである。ある程度バイアスがかかっているのはしかたがない。だから僕はどこまでが事実でどこからが予想で、どの部分が夢を語っているのかをちゃんと区別しながら読もうと心がけていた。
サイエンスZEROでお話しになる先生の印象は誠実だったし、本書の後半にお書きになっているご自身の大学時代から現在に至るまでの研究生活のことを読んだとき、人工知能研究の冬の時代のことも含めて一貫して真面目に取り組んでいらっしゃったことがわかり、「この人の言うことなら信じられる。」という気持になった。
世代による感覚の違いがもたらすものは?
人工知能がない時代に育ったから僕は恐怖や拒否感を感じるのかもしれない。将来、人工知能が当たり前のように生活の中にある環境に生まれる子供たちは、疑いや拒否感をもつこともなく自然に受け入れるはずだ。私たちとはまったく常識や感性の違う次の世代の若者が、次の時代の社会で判断や取捨選択していくようになる。
このような世代間のギャップは、ずいぶん前から始まっていることは言うまでもない。インターネットやSNS、スマートフォンがない時代に生まれた僕の世代は、そのような技術を素晴らしいと思うし、若い頃はプログラミングやコンピュータ科学、エレクトロニクス技術を学ぶことに熱中していた。
しかしこれから生まれてくる次の世代の若者にとってそれらは空気や水のように身の回りにあるものであり、必要不可欠ではあるものの、研究や勉強のための興味を引き起こす対象ではない。彼らにとっての興味の対象はまさに今生まれつつあるもの、変化しつつあるものなのだと思う。
「変化を受け入れる」というのは人それぞれ自分の人生の長さの中でのことであり、次の世代にとっては「生まれたときからある環境」に過ぎない。将来開発されるとてつもない能力をもつ人工知能を受け入れるかどうか、どのように活用していくかは私たちの世代が判断することではない。私たちとは全く違う感性や習慣、考え方をもつ2世代、3世代後の人たちが判断することだ。その判断が正しいかどうかは、さらに後の子孫が歴史をかえりみて判断するしかないのだと僕は思う。
個人的な感想と期待
「
9次元からきた男」ブロガー特別試写会の後に開かれた講演会の中で、大栗博司先生は「将来、人間にはとても証明できないほど難しい数学の定理を人工知能が解く時代がくるかもしれない。」とおっしゃっていた。機械的な手順で数学の定理のすべてが証明されるわけではないことは「
ゲーデルの不完全性定理」によって証明されてはいるが、証明できてしまう定理もきっとでてくることだろう。そうなると数学者の存在意義はどこに求めればよいのだろうか?フィールズ賞はなくなってしまうのかもしれない。
先日、日立製作所が「
社員の幸福感、AIで測定・個別指南する実験を始めた。」というニュースが報道された。人工知能に相談するなんてばかげているし、そんなことをさせられるのは絶対に嫌だと思った。しかしその反面、在りし日の
大原麗子さんそっくりのアンドロイドが目の前にいたら僕はなんでも相談して癒されたいと思うのも本心だ。何が正しく、何が間違っているかなどその時々の気分や状況に左右されてしまう。
ガンの早期発見や自動車の自動運転、自然災害の予測、人類に平和をもたらすような研究ならば大歓迎だ。自分にとって、そして社会や国にとって何がプラスで何がマイナスになるのか、しっかり考えながら人工知能の今後を見ていきたいと思う。
しめくくり
このように、本書を読むことで技術的なことだけでなく社会や人類の未来について、自分がどう感じるかも含めて深く考えさせられた。人工知能の入門書としては最適だ。
著者の松尾先生は本書と同じテーマで次のような講演を行っているのでご覧いただきたい。講演80分+質疑20分の構成でAIの歴史から展望までを一般人向けに解説している。
『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』松尾豊東京大学准教授セッション
次に読む本は
本書を読んでディープラーニングそのものについて、もっと詳しく知りたいと思うようになった。深層学習の「層」が深くなることによる抽象化のことを特に知りたい。抽象化すれば何でも人間の思考や感覚に近くなるものなのか僕にはよく理解できていないからだ。
あまり専門的過ぎず、適度に知的好奇心を満たせそうな本では、次の2冊が気になっている。
「
脳・心・人工知能 数理で脳を解き明かす:甘利俊一」(
Kindle版)
![]()
著者は3年半前に紹介した「
情報理論」という本を書いた甘利俊一先生だ。
そして2冊目はこの本がよさそうだ。
「
機械学習と深層学習 ―C言語によるシミュレーション―:小高知宏」
![]()
関連ページ:
【保存版】人工知能って何?歴史や将来の可能性を10分で理解できるまとめ【2016年度】
http://www.stay-minimal.com/entry/aboutartificialIntelligence
応援クリックをお願いします。
![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()
![人気ブログランキングへ]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
「
人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの: 松尾豊」(
Kindle版)
![]()
内容紹介:
いま、将棋やクイズ番組など「人工知能vs人間」の戦いがあちこちで起こっている。2014年の英オックスフォード大学の研究報告では、今後10年から20年ほどで、人工知能を含むITの進化の影響によって、米国の702の職業のうち約半分が失われる可能性があると述べている。
最先端の人工知能技術「ディープラーニング」をめぐっては、グーグルやフェイスブックなどが数百億円規模の激しい投資・人材獲得合戦を展開。一方で、宇宙物理学者のスティーブン・ホーキング博士や、実業家のイーロン・マスク、ビル・ゲイツなどが、「人工知能は人類を滅ぼすのではないか」との懸念を相次いで表明した。
そのテクノロジーは、ヒトを超える存在を生み出すのか。人間の仕事を、人類の価値を奪うのか。
▼ トップクラスの研究者が解きほぐす、「人工知能」の過去・現在・未来
ディープラーニングの特徴をひと言で言えば、コンピュータが人間のように「気づき」を得るしくみのこと。これまで「人工知能」と呼ばれていたものは、たとえ同じ計算を10万回やっても、1回目と10万回目のやり方は基本的に同じで、「もっと早く計算できる方法」に自ら気づけない。コンピュータの計算能力は飛躍的に上がったが、それは根本解決ではないのだ。しかし、その状況がディープラーニングによって革命的に変わる。
本書では、人工知能学会で編集委員長・倫理委員長なども歴任、日本トップクラスの研究者の著者が、これまで人工知能研究が経てきた歴史的な試行錯誤を丁寧にたどり、その未来像や起きうる問題までを指摘。情報工学・電子工学や脳科学はもちろん、ウェブや哲学などの知見も盛り込み、「いま人工知能ができること、できないこと、これからできるようになること」をわかりやすく解説する。
なお、本書カバーには、ロボットと人間の共生を描いたアニメーション『イヴの時間』より、ヒロインのアンドロイド「サミィ」のイラストを特別にお借りして掲載している。
はじめに――人工知能の春
序章:広がる人工知能――人工知能は人類を滅ぼすか
- 人間を超え始めた人工知能
- 自動車も変わる、ロボットも変わる
- 超高速処理の破壊力
- 人工知能はSF作家になれるか
- 人工知能への研究投資も世界中で加速
- 職を失う人間
- 人類にとっての危機が到来する
- この本の読み方
第1章:人工知能とは何か――専門家と世間の認識のズレ
- まだできていない人工知能
- 基本テーゼ:人工知能は「できないわけがない」
- 人工知能とは何か――専門家の整理
- 人工知能とロボットの違い
- 人工知能とは何か――世間の見方
- アルバイト・一般社員・課長・マネジャー
- 強いAIと弱いAI
第2章:「推論」と「探索」の時代――第1次AIブーム
- ブームと冬の時代
- 「人工知能」という言葉が誕生
- 探索木で迷路を解く
- ハノイの塔
- ロボットの行動計画
- 相手がいることで組み合わせが膨大に
- チェスや将棋で人間に勝利を飾る
- [秘訣1] よりよい特徴量が発見された
- [秘訣2] モンテカルロ法で評価のしくみを変える
- 現実の問題を解けないジレンマ
第3章:「知識」を入れると賢くなる――第2次AIブーム
- コンピュータと対話する
- 専門家の代わりとなるエキスパートシステム
- エキスパートシステムの課題
- 知識を表現するとは
- 知識を正しく記述するために:オントロジー研究
- ヘビーウェイト・オントロジーとライトウェイト・オントロジー
- ワトソン
- 機械翻訳の難しさ
- フレーム問題
- シンボルグラウンディング問題
- 時代を先取りしすぎた「第五世代コンピュータ」
- そして第2次AIブームが終わった
第4章:「機械学習」の静かな広がり――第3次AIブーム(1)
- データの増加と機械学習
- 「学習する」とは「分けること」
- 教師あり学習、教師なし学習
- 「分け方」にもいろいろある
- ニューラルネットワークで手書き文字を認識する
- 「学習」には時間がかかるが「予測」は一瞬
- 機械学習における難問
- なぜいままで人工知能が実現しなかったのか
第5章:静寂を破る「ディープラーニング」――第3次AIブーム(2)
- ディープラーニングが新時代を切り開く
- 自己符号化器で入力と出力を同じにする
- 日本全国の天気から地域をあぶりだす
- 手書き文字における「情報量」
- 何段もディープに掘り下げる
- グーグルのネコ認識
- 飛躍のカギは「頑健性」
- 頑健性の高め方
- 基本テーゼへの回帰
第6章:人工知能は人間を超えるか――ディープラーニングの先にあるもの
- ディープラーニングからの技術進展
- 人工知能は本能を持たない
- コンピュータは創造性を持てるか
- 知能の社会的意義
- シンギュラリティは本当に起きるのか
- 人工知能が人間を征服するとしたら
- 万人のための人工知能
終章:変わりゆく世界――産業・社会への影響と戦略
- 変わりゆくもの
- 産業への波及効果
- じわじわ広がる人工知能の影響
- 近い将来なくなる職業と残る職業
- 人工知能が生み出す新規事業
- 人工知能と軍事
- 「知識の転移」が産業構造を変える
- 人工知能技術が独占される怖さ
- 日本における人工知能発展の課題
- 人材の厚みこそ逆転の切り札
- 偉大な先人に感謝をこめて
おわりに――まだ見ぬ人工知能に思いを馳せて