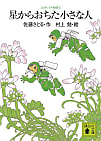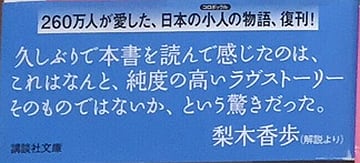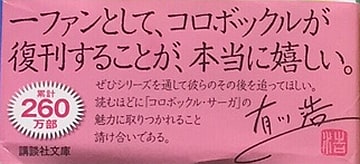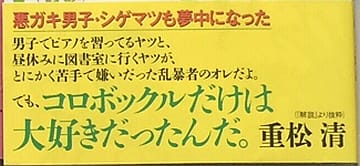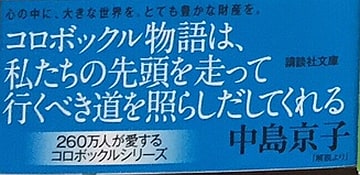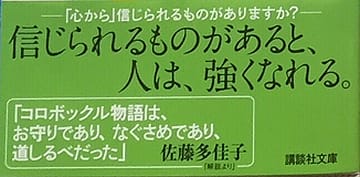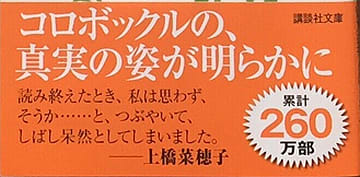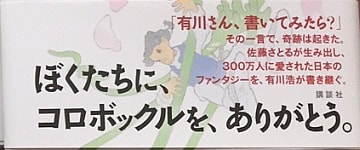理数系書籍のレビュー記事が300冊に達したのでまとめておこう。
僕が理数系書籍を読み始めたいきさつや200冊までの読書で得られたこと、感じたことは2012年12月に書いた「
200冊の理数系書籍を読んで得られたこと」という記事を読んでいただきたい。また毎年発表するお勧め本は「
とね日記賞」というカテゴリーの記事でお読みいただける。
201冊目から100冊を読むのに3年4カ月かかったことになる。(1冊目から200冊目までは6年かかっていた。)2013年3月からは健康維持のためにほとんど毎晩ウォーキングをしているから読書のペースが少し落ちているようだ。仕事するにも趣味を楽しむにも健康が第一だから仕方がない。あと理数系以外の
一般書も意識して読むようになった。僕のような会社員が仕事をしながら勉強を続けられるのは、やはり好きだからできることなのだと思う。
201冊目からの100冊の書名一覧はこの記事の最後に掲載しておいた。
200冊までの勉強は、ニュートン力学から解析力学、熱・統計力学、相対性理論、量子力学、量子テレポーテーション、相対論的量子力学、場の量子論という基礎物理学の道筋をたどり、そのために必要になる数学書も読んできた。数学専攻だったので大学時代に物理学はまったく勉強していなかったから知らないことばかり。ワクワク感、高揚感に満たされる読書を経験することができた。
201冊目からの100冊では、超弦理論を目指しつつもより幅広い分野の本を読んだ。めぼしいものをピックアップして何を学び、どう感じたかをカテゴリー別に書いておこう。番号をクリックすると本のレビュー記事が開く。本から得たこと、感じたことをさらに詳しく読めるほか、関連する本のレビュー記事へのリンクも張ってある。さしずめ「膨大なレビュー記事の迷宮」だ。このページで感想の概要をお読みになってからお入りになるとよいだろう。
熱力学・伝熱学
202: 現代の熱力学:白井光雲
203: フェルミ熱力学:エンリコ・フェルミ
205: 図解 熱力学の学び方 (第2版):北山直方
212: 伝熱工学(東京大学機械工学):庄司正弘
215: 伝熱工学 (JSMEテキストシリーズ):日本機械学会
216: 演習 伝熱工学 (JSMEテキストシリーズ):日本機械学会
207: 熱学思想の史的展開〈1〉:山本義隆
208: 熱学思想の史的展開〈2〉:山本義隆
209: 熱学思想の史的展開〈3〉:山本義隆
210: 高校数学でわかるフーリエ変換:竹内淳
211: 熱の解析的理論:ジョゼフ・フーリエ著、ガストン・ダルブー編纂
200冊までの読書の中で熱力学は何冊かの教科書で学んでいたが、何か足りない気がしていた。たとえば屋外に置いた同じ温度の鉄と木を触ると鉄のほうが冷たく感じる。その理由は大学の物理学科で学ぶ熱力学では説明できず、工学部で学べる伝熱学、伝熱工学で説明される内容だ。熱力学の3法則には時間変数tは含まれず、伝熱学の理論には時間変数tが使われるのが大きく違うところ。そのような違いも実際にそれぞれの分野の教科書を読んで気が付くのだ。
小学生のときに熱伝導、熱放射、対流の3つの方法で熱が伝わることを学ぶが、それを数理的に計算できるようになるためには伝熱学を学ぶ必要がある。バイクの空冷エンジンのフィンや、CPUの冷却板の設計も伝熱学の知識が必要だ。物理学科の教科書では学べないこの分野の本を読んで、実際の問題を解決するための熱の理論を学ぶことができた。
また、白井先生や北山先生の本は熱力学の教科書だが、実生活での熱現象の問題をどのようにして解くかということに重点をおいたユニークな本である。「スペースシャトルの表面に張り付ける耐火レンガは何センチの厚さが必要か?」、という問題と解答も書かれているし、冷蔵庫やエアコンのしくみ(熱交換器)や計算、設計方法も解説されている。
物理学科では熱力学と統計力学をペアにして学ぶ。統計力学は分子の集団的な運動のエネルギーや速度を計算し、熱力学の3法則を導くのだが、そもそも原子や分子が発見されていなければ成り立たない。
仮説としての原子や分子を認めたとしても、統計力学を基礎づけるニュートン力学が確立していた1700年代前半には温度計が無く、熱と温度の区別さえできていなかった。歴史的には「熱学」や「熱力学」のほうが統計力学よりも先に発展していた。その発展史を山本先生の3冊の本で学び、次に熱伝導の理論の創始者であるフーリエが1822年に著した「熱の解析的理論」を読んで科学史に名を残した偉大な学者のレベルに圧倒された。
ブラックホールの熱やエントロピーの問題にも興味があるので学んでみたいが、地球上の熱の問題を解けるようになるほうが先決だと思う。
超弦理論の教科書
236: 初級講座弦理論 基礎編:B.ツヴィーバッハ
237: 初級講座弦理論 発展編:B.ツヴィーバッハ
2013年の暮れにやっと超弦理論に入門することができた。この教科書はタイトルに「初級」と書かれていることからわかるように、2013年9月に日本語で刊行されたばかりのいちばんやさしい教科書である。本書を訳した樺沢宇紀先生から
コメントをいただいたのがうれしかった。
本書は大学学部生でも学べる範囲に限定したトピックを選んで解説している教科書だ。弦理論や超弦理論の数学がどのようなものか、電磁場やエネルギーの流れはどのように多次元空間に広がっているかを知ることができる。難しいテーマ、特にカラビ-ヤウ空間についての解説は含まれていない。初級本とはいえ僕には難しすぎた。「
超弦理論の標準的な教科書」に挑戦したい気持はあるのだが、自分にはまだ無理かな?と踏み出せていないところだ。
超弦理論批判系の本
234: ストリング理論は科学か―現代物理学と数学:ピーター・ウォイト
235: 超ひも理論を疑う:ローレンス M.クラウス
批判本の意見にも目を通しておこうと読んでみたのがこの2冊。特にピーター・ウォイトの本のほうがアンチ度が強い。批判しているポイントは要領を得ていると思う。けれどもその批判が正しいかどうかは今後の実験による検証に委ねられているので、今の段階では判断できないというのが僕の考えだ。僕自身も超弦理論はすごいなと思うところもあるし、疑問を感じている部分もある。でもケプラーのことを思えば、科学を力強く発展させるためにはときに過度な妄想や妄信も必要なんじゃないかな。
大栗先生の科学教養書、超弦理論の科学教養書
206: 強い力と弱い力:大栗博司
229: 大栗先生の超弦理論入門:大栗博司
270: 数学の言葉で世界を見たら: 大栗博司
271: 超ひも理論をパパに習ってみた: 橋本幸士
この3年間に大栗先生は3冊の科学教養書をお書きになっている。ご自身の研究、難解極まりない最先端の科学の現状を一般の人にも知ってもらおうという意欲的な試みだ。税金を使って研究を進めている以上、意義のあることに使われているのだということを伝える義務が科学者にはあるというお考えもあるそうだ。第一線で活躍されている超多忙なお立場であるにもかかわらず、このほかにもNHKの科学教養番組「
神の数式」や日本科学未来館で今日一般公開したばかりの「
9次元からきた男」の監修をされたり、市民向けの講座や講演をなさったり、先生のエネルギーやライフスタイルにはいつもあこがれている。著書を読んで自分自身の学びを深めるとともにブログ記事として紹介することで僕は微力ながら先生の活動のお手伝いをさせていただいている。
橋本幸士先生にも著書の紹介記事を投稿したときにツイッターからご連絡をいただき、とてもうれしかった。
ブライアン・グリーン先生の科学教養書
239: エレガントな宇宙:ブライアン・グリーン
240: 宇宙を織りなすもの(上):ブライアン・グリーン
241: 宇宙を織りなすもの(下):ブライアン・グリーン
242: 隠れていた宇宙(上):ブライアン・グリーン
243: 隠れていた宇宙(下):ブライアン・グリーン
日本語訳された超弦理論の一般向け教養書の中ではいちばん詳しく本格的なシリーズだ。分厚いのでなかなか読めずにいたが、2013年の暮れから集中的に読んでみた。どれも素晴らしい本なのだが、日本とアメリカでは科学教養書のスタイルがずいぶん違うと感じた。グリーン博士の本はまずボリュームが違うし、大人の読者を想定して書かれていると思った。薄い日本語の本と比べて情報量が圧倒的に多いので、話の間の論理的つながりが途切れることがない。(そのぶん冗長に感じる読者もいるだろうが。)そのためにマルチバース(多宇宙)の理論など、にわかには信じられない内容も説得力がでてくるのだ。ページ数の制限から大栗先生の著書では解説されなかった超弦理論の話題がいくつも紹介されている。想像力をかきたてられるシリーズなのだ。
物性物理学
262: 分子運動30講(物理学30講シリーズ):戸田盛和
263: 物性物理30講(物理学30講シリーズ):戸田盛和
268: 基礎の固体物理学: 斯波弘行
279: 固体物理の基礎 上・1 固体電子論概論: アシュクロフト、マーミン
280: 固体物理の基礎 上・2 固体のバンド理論: アシュクロフト、マーミン
281: 固体物理の基礎 下・1 固体フォノンの諸問題: アシュクロフト、マーミン
282: 固体物理の基礎 下・2 固体の物性各論: アシュクロフト、マーミン
285: ゴム弾性(初版復刻版):久保亮五
288: ゴムはなぜ伸びる?:伊藤眞義
この3年間の読書でいちばん大きなことは物性物理学を本格的に学び始めたことだ。金属の性質をその内部の電子の運動によって説明する話が中心テーマだ。アシュクロフト、マーミンの「固体物理の基礎」は1960年代に原著が刊行されたこの分野を代表する教科書で、この大著を読み通せたのが成果だった。今後はさらに他の教科書にもあたって理解を深めていきたい。
久保先生の「ゴム弾性(初版復刻版)」は統計力学を物性物理に応用した本だ。ゴムがフックの法則に従わない、つまり張力と伸びに比例関係がないことは小学生の頃に気が付いていたが、そのメカニズムが数理的に理解できたのがうれしかった。
原子・電子・原子核の発見
219: だれが原子をみたか(岩波現代文庫):江沢洋
220: 新版 電子と原子核の発見(ちくま学芸文庫):S.ワインバーグ
統計力学にしても物性物理学にしても原子や分子があることが前提だ。原子論は古代ギリシアのデモクリトス以来、2000年以上「仮説」のままだった。最終的に原子や分子の存在を証明できたのは20世紀に入ってから、アインシュタインの分子運動論によってである。電子顕微鏡は発明されていなかったからアインシュタインも原子や分子を見たわけではない。どのようなプロセスを経て人類は原子や分子の存在を確信するようになっていったのか?電子や原子核はどのようにして発見されてきたのか?この2冊によってその歴史を詳しく知ることができ、筋道を立てて物事を追及していく物理学の手法に感動した。特に「だれが原子をみたか」をお読みになることをお勧めしたい。2冊とも読むと
電子の発見(1897年)のほうが
アインシュタインの原子の存在証明(1905)より昔であることにも気が付く。
量子力学、場の量子論、素粒子標準模型
292: 趣味で量子力学:広江克彦
221: 場の量子論:坂井典佑
230: 新版 演習場の量子論:柏太郎
222: 「標準模型」の宇宙:ブルース・シューム
223: 完全独習量子力学:林光男
232: ヒッグス粒子の発見:イアン・サンプル
247: 素粒子論はなぜわかりにくいのか:吉田伸夫
274: クォーク 第2版: 南部陽一郎
場の量子論は薄い教科書を選んだことが災いし理解は不十分。量子力学選書のシリーズなど、そこそこボリュームがあり、わかりやすい教科書が刊行されてきたので今後は意欲的に取り組みたい。広江さんの「趣味で量子力学」は期待をはるかに超え充実していた。
この期間に
ヒッグス粒子の発見や
ヒッグス博士のノーベル物理学賞受賞、ニュートリノの質量発見で
梶田先生のノーベル物理学賞受賞されるなど胸躍る大ニュースがあり、ヒッグス粒子やニュートリノの関連本は以前にも増して興味深く読むことができるようになった。
ブログ読者のみなさんへは「ヒッグス粒子の発見:イアン・サンプル」と「「標準模型」の宇宙:ブルース・シューム」、「素粒子論はなぜわかりにくいのか」をお勧めしたい。
現代物理学と現代幾何学のつながり
238: 幾何学の基礎をなす仮説について:ベルンハルト・リーマン
244: 理論物理学のための幾何学とトポロジー I:中原幹夫
245: 理論物理学のための幾何学とトポロジー II:中原幹夫
249: 時間とは何か、空間とは何か: S.マジッド、A.コンヌ、R.ペンローズ他
266: 見えざる宇宙のかたち:シン=トゥン・ヤウ、スティーヴ・ネイディス
現代物理学と現代幾何学のつながりという深淵なテーマ。「理論物理学のための幾何学とトポロジー」は専門的過ぎて理解しきれなかったが、今後の学習方針がわかったのがよかった。
一般向けの教養書ながら、とても難しいのがこの分野だ。「見えざる宇宙のかたち」や「時間とは何か、空間とは何か」は、超弦理論と結びつく領域でどのような現代幾何学が研究されているのかがわかる貴重な本である。どちらの本もあまりの奥深さに驚嘆させられる。
宇宙論
254: 宇宙が始まる前には何があったのか?: ローレンス・クラウス
255: 宇宙創成はじめの3分間 (ちくま学芸文庫):S. ワインバーグ
256: ワインバーグの宇宙論(上)ビッグバン宇宙の進化
257: ワインバーグの宇宙論(下): ゆらぎの形成と進化
296: ブラックホール・膨張宇宙・重力波 一般相対性理論の100年と展開:真貝寿明
もともと宇宙論にはあまり関心がなかったが「宇宙が始まる前に何があったか?」や2013年6月から7月にかけて放送された「
NHK宇宙白熱教室」でこの分野の素晴らしさ、面白さにも開眼することができた。
その後、超一流の素粒子物理学者が書いた「ワインバーグの宇宙論」という専門書に挑戦する。理解は不十分ながら、老科学者がたったひとりでビッグバンから現代に至る宇宙膨張や温度、組成、揺らぎの変化をコンピュータを使わず超絶技巧を駆使した手計算で解明していくという内容に圧倒させられた。
重力波の直接検出に成功というニュースもつい最近のことである。「ブラックホール・膨張宇宙・重力波」はその直前に刊行された教養書だ。このニュースを理解するのにはまさにうってつけの本である。一般相対性理論は100年前に発表された古い理論だが、現在もなお研究が進行していること、ブラックホールの研究は、今後劇的に進みそうなので大いに楽しみだ。
古典力学・微積分学発展史
290: 古典力学の形成―ニュートンからラグランジュへ:山本義隆
291: 微分積分学の史的展開 ライプニッツから高木貞治まで:高瀬正仁
293: 微分積分学の誕生 デカルト『幾何学』からオイラー『無限解析序説』まで:高瀬正仁
200冊までの読書で『プリンキピア』を著したニュートンの偉業に驚嘆したが、ニュートンでも到達できできなかったこと、ニュートンの限界を知ったのが「古典力学の形成」という本だった。ニュートンは古典力学の創始者であったに過ぎず、その後の微積分学の発展がラグランジュの解析力学に昇華していくことで古典力学はようやく完成したのである。解析力学の方程式を使えば静力学の問題でも動力学の問題でも半自動的に解を求めることができる。ラグランジュによるこの万能な理論が編み出されるまでには、多くの科学者、数学者の貢献が必要で200年の年月がかかっていたのだ。上の3冊を読んでニュートンの限界、その後の古典力学と微積分学の発展史を詳細に知ることができた。
解析力学
233: よくわかる解析力学:前野昌弘
ニュートン力学が一般化、抽象化された先にラグランジュによる解析力学(=古典力学)の完成があった。その後、解析力学はハミルトンによってもうひとつの形式で記述され現在私たちが学んでいる理論になった。そしてマクロな世界を支配している解析力学は自然な形でミクロの世界を支配する量子力学の世界へ私たちを導いていたのだ。
200冊までに読んだ本の感想記事では「古典物理学から前期量子論や量子力学の発見へ至る「橋」が2つあることに感動。」と書いたが、前野先生の本を読むと橋は6つあることがわかり解析力学の普遍性に感動。天体力学のようなマクロの力学から素粒子物理のようなミクロの世界まであらゆるスケールの現象に適用できるすごい理論だ。先生の教科書のわかりやすさにも感動した。
- ハミルトン主関数から(光)量子にかかる橋
- ハミルトン-ヤコビ方程式からシュレーディンガー方程式にかかる橋
- ハミルトニアンを使った時間発展の式からハイゼンベルクの運動方程式にかかる橋
- 最小作用の原理からファインマンの経路積分にかかる橋
- ポアッソン括弧から量子力学における交換関係にかかる橋
- 解析力学の位相空間の面積から量子力学の不確定性関係にかかる橋
磁力・磁性・重力の発見
297: 磁力と重力の発見〈1〉古代・中世:山本義隆
298: 磁力と重力の発見〈2〉ルネサンス:山本義隆
299: 磁力と重力の発見〈3〉近代の始まり:山本義隆
300: すごい! 磁石: 宝野和博、本丸諒
物性物理学を学ぶ中で磁石に磁力が発生する原因や性質を学ぶことができたが、天然磁石や磁力は近代科学が始まる前にどのように考えられていたのか?このあたりのことには全く無知だったので山本先生の3冊の本で学んだ。
正しい理解に到達するまで、とんでもない誤解や妄想の時代がこれほど長い間続いていたことに唖然とした。そして第3巻ではケプラーの3法則がどのように導かれたか、ケプラーが惑星の公転の原因が磁力だと考えていたことが紹介される。一見とんでもない説だが、本書を読むとそれがいかに意義のある発想だったこと、ニュートンが万有引力を発見するためには、ケプラーだけでなくロバート・フックの協力も必要だったことが詳細に書かれている。昔の研究者の本当の姿や実績は現代の視点から考えるだけではわからないのだということを強く感じた。
また「すごい!磁石」では、現代の磁石の研究開発の最前線を知り、知識欲を満たしたと同時にこの分野の発展への期待感が大いに高まった。
マイコン、CPUの黎明期
225: マイ・コンピュータ入門―コンピュータはあなたにもつくれる:安田寿明
226: マイ・コンピュータをつくる―組み立てのテクニック:安田寿明
227: マイ・コンピュータをつかう―周辺機器と活用の実際:安田寿明
228: マイクロコンピュータの誕生―わが青春の4004:嶋正利
1970年代にマイコンを自作した先駆者、安田寿明先生の「
マイコン3部作」は当時中学生だった僕が熱中した本だ。内容をほとんど忘れてしまったので、あらためて読んでみた。マイコンがキットとして販売される以前のことである。安田先生は1972年に試作品として日本に20個だけ出荷されたCPU (Intel 8008)うちの1個を8万5千円でやっと手に入れ、その他の回路はすべて自作してマイコンを組み上げたのだ。個人が所有した(おそらく)日本で初めてのコンピュータである。先生が忙しい本業の合間をぬって趣味として熱中したマイ・コン(My Computer)制作。さぞ楽しかったのだろうなぁと思いながら読ませていただいた。
安田先生がマイコン制作を楽しめたのもCPUが開発されたおかげである。「マイクロコンピュータの誕生」は世界初のCPU Intel 4004の開発者のおひとり、嶋正利先生のCPU開発ストーリーである。この本の紹介記事を投稿して数ヵ月後、嶋先生から直接メールをいただいたときは、びっくりすると同時にとてもうれしかった。
数学の教科書
246: 代数学I 群と環:桂利行
248: 演習 群・環・体入門:新妻弘
253: 代数系入門: 松坂和夫
261: 素数夜曲―女王陛下のLISP:吉田武
265: 現代数学への招待:多様体とは何か:志賀浩二
269: ガロア理論の頂を踏む: 石井俊全
283: トポロジー入門: 松本幸夫
289: 圏論の歩き方(日本評論社)
294: 定本 解析概論:高木貞治
295: なっとくする複素関数:小野寺嘉孝
もっと専門的な教科書を読みたかったのだが、結果として大学2,3年程度の本が多くなってしまった。けれども代数学系、幾何学系、解析学系のバランスはよいと思う。特に「トポロジー入門」をお書きになった松本先生とお会いできたこと、「解析概論」を通読したことが自分にとってのハイライトだったと思う。
数学とは何か?
258: 数学とは何か(原書第2版):R.クーラント、H.ロビンズ、I.スチュアート
259: 無限をつかむ: イアン・スチュアートの数学物語
260: 数学とは何か―アティヤ 科学・数学論集
286: 数学の大統一に挑む:エドワード・フレンケル
これも深淵で大好きなテーマ。どの本からも刺激を受けた。一般の方に読んでいただける本ばかりだ。特に「数学の大統一に挑む:エドワード・フレンケル」は「
NHK数学ミステリー白熱教室」として放送されたのでお読みになった方も多いことだろう。ラングランズ予想は今後どのように展開していくのだろうか?数学と物理学のつながりはもっと多くの事例が見つかっていくのだろうか? 最先端の数学を自分が理解できるようになるとは思えないが、強く魅了されるテーマである。
ファインマン先生関連本
250: ファインマンさんは超天才: C.サイクス
251: 聞かせてよ、ファインマンさん: R.P.ファインマン
大好きなファインマン先生のことは2年前に「
ファインマン先生の自伝本と講演本」という記事で紹介していたのだが、201冊目以降の3年間ではこの2冊しか読んでいなかった。ほとんどの本は読んでしまったから、これからも少しずつ未読の本を読んでいこう。
電子工学、通信技術
264: 電気通信物語―通信ネットワークを変えてきたもの:城水元次郎
幕末の日本にペリー提督が持ち込んだ有線式のモールス電信機の話から2000年あたりのインターネットや携帯電話まで。電気を用いた情報通信について技術や関連設備、国家や企業がどのように展開、競争していったかの歴史を詳細に解説している本だ。とても面白いのでぜひお読みになっていただきたい。
DNA関連
273: 二重螺旋 完全版: ジェームズ・D. ワトソン
275: DNA (上)―二重らせんの発見からヒトゲノム計画まで: ジェームズ・D. ワトソン
276: DNA (下)―ゲノム解読から遺伝病、人類の進化まで: ジェームズ・D. ワトソン
3冊とも生命の設計図の根底にあるのはDNAの中の原子や分子なのだということを再認識させられた本だ。そしてDNA以前の分子生物学やゲノム計画について知ることができた。僕にとっては未知の分野だっただけにとても新鮮だった。
また、小さな細胞の中にあるとても細くて長いDNAの二重らせんが、なぜ絡まずに2つの細胞に分かれることができるのだろうか?この謎はDNA二重らせん構造が発見された1953年からだいぶ経った1995年に数学の理論としてようやく解明された。このことについては昨年書いた「
多次元空間へのお誘い」という連載記事の第14回「
DNAの複製について」という記事で解説しておいた。
気象関連
284: 知識ゼロからの異常気象入門:斉田季実治
287: 気象キャスター寺川奈津美 はれますように~未来はきっと変えられる
九州地方では先週から心配な日々が続いているが、近年は特に自然災害や気象災害が目立ってきている。気象予報士の斉田季実治さんも熊本県のご出身だ。皆が関心をもつべきテーマであることからこの2冊を読んだ。
昨年は寺川奈津美さんの朝日カルチャーセンターの講座も受講させていただいた。(
参照記事)にこやかにお話しされる講座の中では気象災害をどのように予報、伝達しているかについて真剣な顔でお話しされていたことが強く印象に残っている。その後、寺川さんはNHKニュースでの仕事を離れ、この4月からはフジテレビの「
直撃LIVE グッディ!」の気象キャスターとして活躍されている。
原発関連
277: 原子・原子核・原子力―わたしが講義で伝えたかったこと:山本義隆
278: 福島の原発事故をめぐって― いくつか学び考えたこと:山本義隆
これも広く国民全体が関心をもち、国論が二分されているテーマだ。山本先生がどのようにお考えになっているか知りたかったので読んでみた。「原子・原子核・原子力―わたしが講義で伝えたかったこと」は物理を学んだ高校生以上、「福島の原発事故をめぐって」は数式のない文章だけで書かれた本なので一般の人でも読むことができる。
理数系書籍としてはカウントしなかったが、原発関連ではあと「
知ろうとすること。(新潮文庫): 早野龍五、糸井重里」という本も読んでいる。
関連記事:
200冊の理数系書籍を読んで得られたこと
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/1b92c958e54960246be16b564c6b8c8e
超弦理論に至る100冊の物理学、数学書籍
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d37fe65a84df23cca2af7ecebb83cfc6
超弦理論への最短ルート: 40冊の物理学、数学書籍
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d8deb00ae3b5b9e0e9a04f3c3ecfb11e
高校生にお勧めする30冊の物理学、数学書籍
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f79ac08392742c60193081800ea718e7
祝: とね日記はおかげさまで10周年!(2015年2月に投稿した記事)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b6227a305e06bc794b4cd9dd2dcc87f8
応援クリックをお願いします!
![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()
![人気ブログランキングへ]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
201冊目から300冊目までの書名一覧
シリーズ物が連続するように実際に読んだのとは順番を少し変えている。記事本文で取り上げていない本はGoogleから「書名 とね日記」というキーワードで検索すれば、レビュー記事を見つけることができる。
201: 量子力学のイデオロギー増補新版:佐藤文隆
202: 現代の熱力学:白井光雲
203: フェルミ熱力学:エンリコ・フェルミ
204: 明解量子重力理論入門:吉田伸夫
205: 図解 熱力学の学び方 (第2版):北山直方
206: 強い力と弱い力:大栗博司
207: 熱学思想の史的展開〈1〉:山本義隆
208: 熱学思想の史的展開〈2〉:山本義隆
209: 熱学思想の史的展開〈3〉:山本義隆
210: 高校数学でわかるフーリエ変換:竹内淳
211: 熱の解析的理論:ジョゼフ・フーリエ著、ガストン・ダルブー編纂
212: 伝熱工学(東京大学機械工学):庄司正弘
213: 今この世界を生きているあなたのためのサイエンス〈1〉:リチャード・A.ムラー
214: 今この世界を生きているあなたのためのサイエンス〈2〉:リチャード・A.ムラー
215: 伝熱工学 (JSMEテキストシリーズ):日本機械学会
216: 演習 伝熱工学 (JSMEテキストシリーズ):日本機械学会
217: 世界を変えた17の方程式:イアン・スチュアート
218: 宇宙がわかる17の方程式―現代物理学入門:サンダー バイス
219: だれが原子をみたか(岩波現代文庫):江沢洋
220: 新版 電子と原子核の発見(ちくま学芸文庫):S.ワインバーグ
221: 場の量子論:坂井典佑
222: 「標準模型」の宇宙:ブルース・シューム
223: 完全独習量子力学:林光男
224: 宇宙になぜ我々が存在するのか:村山斉
225: マイ・コンピュータ入門―コンピュータはあなたにもつくれる:安田寿明
226: マイ・コンピュータをつくる―組み立てのテクニック:安田寿明
227: マイ・コンピュータをつかう―周辺機器と活用の実際:安田寿明
228: マイクロコンピュータの誕生―わが青春の4004:嶋正利
229: 大栗先生の超弦理論入門:大栗博司
230: 新版 演習場の量子論:柏太郎
231: 高校数学でわかる統計学:竹内淳
232: ヒッグス粒子の発見:イアン・サンプル
233: よくわかる解析力学:前野昌弘
234: ストリング理論は科学か―現代物理学と数学:ピーター・ウォイト
235: 超ひも理論を疑う:ローレンス M.クラウス
236: 初級講座弦理論 基礎編:B.ツヴィーバッハ
237: 初級講座弦理論 発展編:B.ツヴィーバッハ
238: 幾何学の基礎をなす仮説について:ベルンハルト・リーマン
239: エレガントな宇宙:ブライアン・グリーン
240: 宇宙を織りなすもの(上):ブライアン・グリーン
241: 宇宙を織りなすもの(下):ブライアン・グリーン
242: 隠れていた宇宙(上):ブライアン・グリーン
243: 隠れていた宇宙(下):ブライアン・グリーン
244: 理論物理学のための幾何学とトポロジー I:中原幹夫
245: 理論物理学のための幾何学とトポロジー II:中原幹夫
246: 代数学I 群と環:桂利行
247: 素粒子論はなぜわかりにくいのか:吉田伸夫
248: 演習 群・環・体入門:新妻弘
249: 時間とは何か、空間とは何か: S.マジッド、A.コンヌ、R.ペンローズ他
250: ファインマンさんは超天才: C.サイクス
251: 聞かせてよ、ファインマンさん: R.P.ファインマン
252: 数学の教科書が言ったこと、言わなかったこと:南みや子
253: 代数系入門: 松坂和夫
254: 宇宙が始まる前には何があったのか?: ローレンス・クラウス
255: 宇宙創成はじめの3分間 (ちくま学芸文庫):S. ワインバーグ
256: ワインバーグの宇宙論(上)ビッグバン宇宙の進化
257: ワインバーグの宇宙論(下): ゆらぎの形成と進化
258: 数学とは何か(原書第2版):R.クーラント、H.ロビンズ、I.スチュアート
259: 無限をつかむ: イアン・スチュアートの数学物語
260: 数学とは何か―アティヤ 科学・数学論集
261: 素数夜曲―女王陛下のLISP:吉田武
262: 分子運動30講(物理学30講シリーズ):戸田盛和
263: 物性物理30講(物理学30講シリーズ):戸田盛和
264: 電気通信物語―通信ネットワークを変えてきたもの:城水元次郎
265: 現代数学への招待:多様体とは何か:志賀浩二
266: 見えざる宇宙のかたち:シン=トゥン・ヤウ、スティーヴ・ネイディス
267: スーパーシンメトリー ― 超対称性の世界:ゴードン・ケイン
268: 基礎の固体物理学: 斯波弘行
269: ガロア理論の頂を踏む: 石井俊全
270: 数学の言葉で世界を見たら: 大栗博司
271: 超ひも理論をパパに習ってみた: 橋本幸士
272: 「知」の欺瞞:アラン・ソーカル、ジャン・ブリクモン
273: 二重螺旋 完全版: ジェームズ・D. ワトソン
274: クォーク 第2版: 南部陽一郎
275: DNA (上)―二重らせんの発見からヒトゲノム計画まで: ジェームズ・D. ワトソン
276: DNA (下)―ゲノム解読から遺伝病、人類の進化まで: ジェームズ・D. ワトソン
277: 原子・原子核・原子力―わたしが講義で伝えたかったこと:山本義隆
278: 福島の原発事故をめぐって― いくつか学び考えたこと:山本義隆
279: 固体物理の基礎 上・1 固体電子論概論: アシュクロフト、マーミン
280: 固体物理の基礎 上・2 固体のバンド理論: アシュクロフト、マーミン
281: 固体物理の基礎 下・1 固体フォノンの諸問題: アシュクロフト、マーミン
282: 固体物理の基礎 下・2 固体の物性各論: アシュクロフト、マーミン
283: トポロジー入門: 松本幸夫
284: 知識ゼロからの異常気象入門:斉田季実治
285: ゴム弾性(初版復刻版):久保亮五
286: 数学の大統一に挑む:エドワード・フレンケル
287: 気象キャスター寺川奈津美 はれますように~未来はきっと変えられる
288: ゴムはなぜ伸びる?:伊藤眞義
289: 圏論の歩き方(日本評論社)
290: 古典力学の形成―ニュートンからラグランジュへ:山本義隆
291: 微分積分学の史的展開 ライプニッツから高木貞治まで:高瀬正仁
292: 趣味で量子力学:広江克彦
293: 微分積分学の誕生 デカルト『幾何学』からオイラー『無限解析序説』まで:高瀬正仁
294: 定本 解析概論:高木貞治
295: なっとくする複素関数:小野寺嘉孝
296: ブラックホール・膨張宇宙・重力波 一般相対性理論の100年と展開:真貝寿明
297: 磁力と重力の発見〈1〉古代・中世:山本義隆
298: 磁力と重力の発見〈2〉ルネサンス:山本義隆
299: 磁力と重力の発見〈3〉近代の始まり:山本義隆
300: すごい! 磁石: 宝野和博、本丸諒
![]()
![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()
![人気ブログランキングへ]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()