「磁力と重力の発見〈3〉近代の始まり:山本義隆」
内容紹介:
第3巻でようやく近代科学の誕生に立ち会う。霊魂論・物活論の色彩を色濃く帯びたケプラーや、錬金術に耽っていたニュートン。重力理論を作りあげていったのは彼らであり、近代以降に生き残ったのはケプラー、ニュートン、クーロンの法則である。魔術的な遠隔力は数学的法則に捉えられ、合理化された。壮大な前科学史の終幕である。
2003年刊行、432ページ。
著者について:
山本義隆(やまもとよしたか)
1941年大阪生まれ。大阪府出身。大阪市立船場中学校、大阪府立大手前高等学校卒業。1964年、東京大学理学部物理学科卒業。 東京大学大学院博士課程中退。
1960年代、学生運動が盛んだったころに東大全共闘議長を務める。1969年の安田講堂事件前に警察の指名手配を受け地下に潜伏するが、同年9月の日比谷での全国全共闘連合結成大会の会場で警察当局に逮捕された。日大全共闘議長の秋田明大とともに、全共闘を象徴する存在であった。
学生時代より秀才でならし、大学では物理学科に進んで素粒子論を専攻した。大学院在学中には、京都大学の湯川秀樹研究室に国内留学しており、物理学者としての将来を嘱望されていたが、学生運動の後に大学を去り、大学での研究生活に戻ることはなかった。
その後は予備校教師に転じ、駿台予備学校では「東大物理」などのクラスに出講している。一方で科学史を研究しており、当初エルンスト・カッシーラーの優れた翻訳で知られたが、後に熱学・熱力学や力学など物理学を中心とした自然思想史の研究に従事し今日に至っている。遠隔力概念の発展史についての研究をまとめた『磁力と重力の発見』全3巻は、第1回パピルス賞、第57回毎日出版文化賞、第30回大佛次郎賞を受賞して読書界の話題となった。
山本義隆: ウィキペディアの記事 Amazonで著書を検索
理数系書籍のレビュー記事は本書で299冊目。
僕がこの本を読みたいと思ったきっかけは惑星の公転の原因が磁力だとケプラーが考えていたのを知ったことだった。チコ・ブラーエの20年におよぶ惑星の位置観測の記録から火星の公転が楕円軌道であることを導き、ケプラーの3法則を打ち立てた数学者ケプラーがなぜ磁力に公転運動の理由を求めたのか?太陽や惑星が磁石でできているとでも思っていたのだろうか?
磁力について正しい理解に達していなかった近代以前、磁力は「隠された力」であり「自然魔術」のひとつだった。一方で数学の手法を用い、もう一方で合理的な説明を放棄したとも見える磁力説を提唱していたことに違和感をもっていたのだ。
しかし「宇宙の神秘(1596)」、「新天文学(1609)」「宇宙の調和(1619)」というケプラー3部作の中で、彼は太陽系の惑星軌道半径が互いに内接する正多面体によって説明できるとか、惑星の公転運動によって奏でられる「メロディ」の研究を紹介している。それらにくらべれば磁力説はまだ許容できるものなのかもしれない。
著者の山本先生が本書を執筆を思い立ったのもまさに同じ理由だと「あとがき」にお書きになっている。近代に入ってもなお魔術思想は影響を残していた。しかし魔術思想は近代科学の誕生の足を引っ張っていたわけではなく、むしろ後押ししていたという意外な事実が本書を読むとわかる。
ケプラーに多大な影響を与えたウィリアム・ギルバートは著書『磁石論(1600)』によって地球が巨大な磁石であることを明確に示した。またコペルニクス、ケプラー、デカルト、ガリレイ、フック、ニュートンに至る過程でどのような発想の転換がおきていたか。イギリスの王立協会が設立される過程、原子仮説に基づく機械論による自然理解は17世紀にロバート・ボイルらによってどのように変化していったか。そしてその後クーロンらによって電気力と磁気力の測定されて両者がともに逆二乗法則に従って減衰していることが導かれ、近代の電磁気学が誕生するまでの経緯が詳細に解説されている。
本シリーズのタイトルは「磁力と重力の発見」であるが、重力はようやく第3巻で詳しく取り上げられる。アリストテレス哲学では宇宙の中心である地球の中心に戻ろうとする自然な運動として考えられていた重力は、どのような変遷をへて遠隔力としての重力に移行していったのか、そして早い段階で遠隔力であることが経験的に知られていた磁力は、原子仮説に基づく機械論の全盛期にどのように考えられていたのか。このあたりも本書を読んで得られる醍醐味のひとつである。
また天文学と物理学の区別が現代のスタイルに分かれていったのもこの時代である。ケプラー以前の天文学はコペルニクスの地動説の太陽系モデルも含めて「幾何学」だったからだ。天文学は日食や月食の予測、占星術、暦の作成をおこなえれば十分であり、天体間に働く力や運動はむしろ定性的な理解や哲学の範疇に属する「自然哲学」だった。ケプラー以降、天体間に働く力を関数であらわし数学を使って計算するようになり、力や運動という動力学の考え方が天文学の概念を近代的なものに変化させていった。天文学が単なる幾何学から物理学へ変化し始めたのである。
第2巻までは読むのが大変だったが、第3巻は行きつ戻りつはあるものの近代科学へ向かって比較的順調に進んでいくので好奇心が途切れずに読み通すことができた。ケプラーの洞察力の凄さに感動し、ガリレイやデカルト、ニュートンに対するイメージも若干修正された。そしてこれまでは「フックの法則」によってしか知らなかったロバート・フックがニュートンに与えた影響を知ったのも僕には初めてのことだった。
章立ては次のとおりだ。ヨーロッパ史だと西暦1600年頃から1800年頃まで。
第17章:ウィリアム・ギルバートの『磁石論』
第18章:磁気哲学とヨハネス・ケプラー
第19章:一七世紀機械論哲学と力
第20章:ロバート・ボイルとイギリスにおける機械論の変質
第21章:磁力と重力―フックとニュートン
第22章:エピローグ―磁力法則の測定と確定
第3巻の登場人物はとても多いので、主だった人物についてのみ年代順に、そして磁力と重力についての業績についてだけ紹介しておく。
ウィリアム・ギルバート(1544-1603)
著書『磁石論(1600)』によって次のことを述べた。
- 地球が巨大な磁石であることを提唱。
- 地球のレプリカとして球形磁石「テレラ(小地球)」を用いた磁力の実験を行った。
- 磁気哲学を提唱した。
- 検電器を発明し、琥珀現象(静電引力)の実験を行い、静電気研究の出発点を築いた。
- 彼の行った琥珀の実験は定性的なものにとどまっていた。
- 電気力は電気発散気と呼んだ物質による近接作用と考えた。
- 磁石にはその磁力がおよぶ「作用圏」があると考えた。
- 磁気の作用圏は実在的なものではなく、磁力は遠隔作用だと考えていた。
- 電気的な運動はおもに質料(materia)によって、磁気的な運動はおもに形相(forma)によって実現されると考えていた。
- 電気力の原因の質料は電気発散気という物質であり、磁力の原因の形相は非物質だと考えた。
- 地球が持つ磁力は地球自身の自転軸の方向を決め、さらに自転運動を引き起こすと考えた。その意味で彼はコペルニクスの地動説をいち早く取り入れていた。
- このように主張しつつも、地球を含むあらゆる天体は球であり、すべての球は創造主によって与えられた霊魂によって支配されて運動が決定づけられ、磁石さえも霊魂を持つと考えていた。
つまり地球は霊魂を有していることと磁性によりみずから回転し、みずからを方向づけるということは切り離して考えることができない。その2つをもってギルバートは地動説を受け入れることができたのである。
コルチェスターのウィリアム・ギルバートの著作、『磁石論』出版400周年を記念して
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/stern-j/demagint_j.htm
『磁石論』の英語版はここに公開されている。邦訳されている「磁石(および電気)論 新版」は150ページしかないので部分訳だ。
https://archive.org/details/williamgilbertc00wriggoog
ヨハネス・ケプラー(1571-1630)
「宇宙の神秘(1596)」、「新天文学(1609)」「宇宙の調和(1619)」というケプラー3部作によりケプラー3法則を提唱した。ケプラーはギルバートの『磁石論(1600)』を読んで多大な影響を受けていた。
コペルニクスの地動説の太陽系モデルでは惑星の軌道は真円である。コペルニクスにとって地球の公転軌道の中心はいわば「平均太陽」の位置である。軌道が楕円であることを確信していたケプラーは、楕円の中心(2つの焦点の中点)という何もない場所に「影響力」の中心があるはずがないことに気が付いていた。
ケプラーは惑星の公転運動の原因を当初は「運動霊」であるとしていたが、後に原因を磁力に求めた。それはギルバートの『磁石論(1600)』による影響である。ケプラーは太陽、惑星、月などの天体はすべて磁石であると考えていた。しかし磁力は引力として働くのではない。惑星に及んでいる太陽の磁力の作用圏は太陽が自転することによって回転し、地球を軌道の接線方向に引きずって公転運動を引き起こすと考えていた。また磁力が太陽から離れるに従って減衰することはギルバートの理論から知っていたが、作用圏を地球の公転面だけに限って考えたために逆一乗則に従って磁力が減衰するという理論だった。実際、彼は惑星の公転速度をもとに太陽の自転速度を3日だと割り出したが、もちろん見当はずれな値だ。
ケプラーの業績で見逃してはならないことは、磁力を起源とした誤った前提のもとに打ち立てられていたとはいえ幾何学に過ぎなかった惑星の運動の理論を動力学へ移行させたことにある。そして太陽が6個の惑星に及ぼす力、地球が月に及ぼす力、木星が4個の衛星に及ぼす力が同種類のものであることをもケプラーの法則は示唆していた。また静止した状態に限定されていたが「慣性(inertia)」という言葉を創ったのもケプラーである。これらのことが後にニュートンの万有引力発見へと結びついていく。
高校物理でケプラーの3法則は1~2ページで解説され、「ケプラーの法則の発見が物理学の根幹となる万有引力の法則の発見へとつなっていきます。」と簡潔に記述されている背後に、これほど壮大な想像力と深い洞察、精緻で厖大な計算があったことに僕は感動した。
邦訳された「宇宙の神秘(1596)」は376ページなのでなんとか読み切ったのだが、ケプラーの第1法則、第2法則を発表した「新天文学(1609)(目次情報)」と第3法則を発表した「宇宙の調和(1619)」はどちらも650ページ前後の大著で微積分誕生以前の数学手法、とりわけ三角比を複雑に組み合わせて用いる古代ギリシャのユークリッド幾何学で書かれた本である。僕はこの3冊を持っているが未読の2冊を読み解く自信はまったくない。
新天文学(ラテン語版)
https://www.kyoto-su.ac.jp/lib/kichosyo/kepler/pages/jk_001.html
宇宙の調和(英語版)
http://sacred-texts.com/astro/how/index.htm
ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)
ガリレイはみずから制作した望遠鏡を使って惑星の衛星の発見、太陽黒点や月面の観察をしたことにより、自然の見方や観測方法に根底的な変革をもたらした。
望遠鏡による太陽黒点や月面の凹凸は地上で観測される大地の起伏と同様に不規則で、天体を構成する物質も地上にある物質と同種のものであるというインスピレーションをもたらしたのだ。もともと神が創造した天体は天界という別世界にある完全な球であり、太陽黒点のようなしみや月面に凹凸などあるはずがないと考えられていたからだ。天体も物質であるのなら質量を持つのだろうという意味において、ニュートンの万有引力の発見に結びつくヒントになったといえよう。
ガリレイは地上の物体の運動法則、落体の法則を実験により導き、近代的な意味で世界最初の科学者と呼ばれている。そして彼の自然観は物質が無性質、不活性で受動的であるという機械論である。
しかしガリレイはケプラーの楕円軌道の意義を認めることができず、万有引力の発見を取り逃がした。遠隔力としての重力も受け入れることができなかった。ガリレイにとって太陽系は本質的に物理学の問題ではなかったのである。
またガリレイには力の概念が完全に欠落していて、その意味で彼の力学は動力学に到達せず数学的な運動学にとどまっていた。望遠鏡で惑星を観測していたものの、惑星の運動についての理論らしきものを何ひとつ作り出していない。天体力学という観念をとらえるのに完全に失敗していたのである。地動説という新しい宇宙像のために闘った殉教者のように言われているが、惑星運動のダイナミズムについては全く無知であったのだ。
本書で強調されているガリレイの業績とは、物体は「なぜ」落下するのかというそれまでの自然学の設問自体を退け、物体は「どのように」落下するのかという問題に守備範囲を限定し、事物や現象の数学的法則性を読み解く手法を創始したことである。そして仮説・論証・実験という近代科学の方法を編み出した。
ルネ・デカルト(1596-1650)
デカルトの自然観も機械論であるが、ガリレイの機械論とかなり異なっていた。彼は「感覚は認識を妨げかねない」ので実験的検証に頼らず演繹的論証のみを重視して自然を理解しようとした。彼は運動の第一原因として「神は宇宙の中につねに同量の運動を保存している」という命題を置き、そこから自然学の基本法則として次の3つの力学原理を導き出している。
第1法則:あらゆるものはできるだけ同じ状態を保とうとする。したがって一度動かされると、いつまでも動き続ける。
第2法則:すべての運動は、それ自身として直線的である。したがって円運動するものはその描く円の中心からつねに遠ざかろうとする。
第3法則:物体はより強力な他の物体と衝突するときには、自分の運動をなんら失わないが、より弱い物体と衝突するときにはその弱い物体に移しただけの運動を失う。
つまりデカルトは「慣性の法則」を初めて定式化し、「運動量の保存則」の萌芽形態を提唱したことで初期の力学理論の発展に大きな功績を残した。
しかし彼の力学は力の概念が欠如した衝突の理論に過ぎない。見かけの遠隔作用は空間に感覚ではとらえられない物質が存在するとし、惑星の運動についても太陽の回りを渦になって回転する微細物質が惑星を押しているからだと説明した。デカルトの「渦動仮説」である。この説の致命的な欠陥は、精密な観測に裏打ちされたケプラーの3法則を同じレベルの精密さで説明できないことにあった。
磁力については磁石や鉄には磁気粒子が通る通孔があり、磁気粒子の運動の結果生じるというあくまで機械論こだわった定性的な理解に留まっていた。
デカルトはコペルニクスの地動説を支持していたとはいえ、あくまで哲学者であり、数学者であったのだ。
ロバート・ボイル(1627-1691)
科学の世界でボイルを有名にしたのは、フックの協力で作り上げた真空ポンプをもちいた一連の大気と真空の実験と、現在「ボイルの法則」と呼ばれている事実の発表だった。彼の物質観は「粒子哲学」である。ボイルは引力を認めず、遠隔力としての引力は直接的接触による衝撃または圧力の結果であるとみなしていた。それゆえ遠隔力の典型である磁力も近接作用として説明されることになる。
ボイルにとって磁化とは純粋に機械的な作用であり、地球の磁力による磁気発散気が通孔をもつ鉄が影響を与えるというものだった。電気力についても電気物質による発散気に起源があるとした。
ロバート・フック(1635-1703)
「フックの法則」で有名なロバート・フックは、重力の原因が磁力であるかどうかを見極めるために、その減衰を数学関数であらわそうとしその関数形が等しければ両者は同じ原因によるものと考えた。彼はそのために重力と磁力が距離によりどのように減衰するかの実験を行った。実験はうまくいかなかったことは容易に想像できるが、魔術的な色彩に彩られていた磁力についての知が近代科学のものに大きく一歩近づいたのである。
またフックは惑星の運動は慣性による軌道接線方向への直線運動に中心物体からの引力による中心方向への加速(屈曲)が重ね合わされたものと考え、惑星運動を正しく解析する道を開いた。この点についてフックはニュートンに意見を求めたことがニュートンの惑星運動理論に大きな寄与をすることになった。
そしてフックは「世界の体系」が3つの仮説によて解明されると主張した。
1)太陽系のすべての天体の運動が距離をへだてて働く相互的な引力(中心力)に支配されていること。
2)すべての曲線運動が慣性運動からの逸れの結果であり、それをもたらす力が上記1)の引力であること。
3)その引力は距離とともに減少すること。そしてその力は逆二乗則に従って減少する。
これらはほとんどニュートンが導いた結論に等しいが、数学的に証明する手腕をフックは欠いていたのである。
フックがそのような境地に達していたことも、ニュートンと同時代を生きた人だということも僕は知らなかったのでまさに目から鱗が落ちる思いがした。
アイザック・ニュートン(1642-1727)
そのようなわけでフックが構想した「世界の体系」を込み入った円錐曲線の諸定理とデリケートな極限操作を駆使し、緻密で早大な数学的体系に仕上げたのがフックより7歳年下のニュートンである。ニュートンはケプラーの3法則から太陽と惑星のあいだに距離の二乗に反比例する引力が働いていることを導き出し、その引力が万有であると仮定し、惑星・衛星の運動ばかりか地球の形状から潮汐までその著書「プリンキピア(1687, 1713, 1726)」で説明してみせた。これは17世紀の素朴な機械論の制約を打ち破って、数理科学としての近代物理学を創始したという偉大な業績である。
以前僕は「万有引力(重力)の原因についてニュートンは理解していなかった。」と否定的な意味合いで紹介したことがあるが、本書を読んでむしろそれは見当違いであることがわかった。つまり、ニュートンは純粋に数学的な手法により万有引力のありようを示すことが自然哲学(物理学)の目的であり、万有引力の「原因」や「本質」、「存在理由」を問うことは目的ではなかったからだ。それらを意図的に排除していたのである。このように、かつてガリレイが運動学にたいしておこなっていた数学的現象主義の立場を、ニュートンは動力学まで押し広めたのである。
ニュートンが導いたのはケプラーの3法則から万有引力という「順問題」であり、万有引力からケプラーの3法則を導くという「逆問題」の導出には成功していなかったことは「古典力学の形成―ニュートンからラグランジュへ:山本義隆」という本に書かれている。「磁力と重力の発見」ではこのことについてふれられていなかった。
順問題の解法:
http://wakariyasui.sakura.ne.jp/p/mech/bannyuu/bannyuu.html
逆問題の解法(英語ページ):
http://galileo.phys.virginia.edu/classes/152.mf1i.spring02/KeplersLaws.htm
ニュートンが生涯に書き残したもののなかには、磁石や磁力について触れている箇所は散見されるが、主題として真正面から論じたものは見当たらない。
シャルル・ド・クーロン(1736-1806)
磁力の減衰がどのような法則に従っているかは、ミュッセンブルークとヘルシャム、カランドリーニ、ジョン・ミッシェル、トビアス・マイヤーなどによって測定、研究されてきたが、逆二乗則に従うことを最終的に導いたのはクーロンの測定によるものだった。クーロンは電気力の減衰が逆二乗則に従うことも測定で求めたことで有名だが、磁力の減衰の法則も彼の業績である。ともに「クーロンの法則」として知られている。磁力の減衰の測定が困難だったのは、磁石が単極でないこと、磁石が広がりをもった物体であることが理由である。測定の詳細は次のページをお読みになっていただきたい。
1777年~1787年:クーロンの法則
http://www.neomag.jp/mag_navi/history/history_08.php
このようにして瞬時に伝わる遠隔力として磁力と電気力、重力が理解されていったのだが、それらが光速で伝わる近接力であることがわかったのは、磁力と電気力については電磁気学と量子力学の完成、重力については一般相対性理論の完成を待たなければならなかった。しかし18世紀からみてそれははるか先の未来の理論である。
この「磁力と重力の発見」3部作をお書きになった後、山本先生は続編として「十六世紀文化革命」2部作、さらに「世界の見方の転換」3部作をお書きになり、「磁力と重力の発見」で語り尽くせなかったことを補っている。これらの本もいずれ読んでみたい。
ブログ記事で紹介できたのは本書のほんのハイライト部分に過ぎず、論理的につながらない箇所や抜けがたくさんでてくるのはやむをえない。記事では紹介できなかった社会的、思想的背景を含めてご理解いただくために、ぜひこの3部作に挑戦していただきたい。そして学校でケプラーの法則やニュートンの万有引力の法則を学ぶ高校生には「磁力と重力の発見」は難しすぎるので、せめて今回のブログ記事だけでも読んでほしいと僕は思うのだ。
「磁力と重力の発見〈1〉古代・中世:山本義隆」
「磁力と重力の発見〈2〉ルネサンス:山本義隆」
「磁力と重力の発見〈3〉近代の始まり:山本義隆」
![]()
![]()
![]()
関連ページ:
永久磁石の歴史と磁気科学の発展
http://www.neomag.jp/mag_navi/history/history_top.php
関連記事:
磁力と重力の発見〈1〉古代・中世:山本義隆
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/75ef1fc1216c255471fdbf65cc3a0c49
磁力と重力の発見〈2〉ルネサンス:山本義隆
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/16b61843d410a867f942f3f8aef13865
応援クリックをお願いします!
![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()
![人気ブログランキングへ]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
「磁力と重力の発見〈3〉近代の始まり:山本義隆」
![]()
第17章:ウィリアム・ギルバートの『磁石論』
- ギルバートとその時代
- 『磁石論』の位置と概要
- ギルバートと電気学の創設
- 電気力の「説明」
- 鉄と磁石と地球
- 磁気運動をめぐって
- 磁力の本質と球の形相
- 地球の運動と磁気哲学
- 磁石としての地球と霊魂
第18章:磁気哲学とヨハネス・ケプラー
- ケプラーの出発点
- ケプラーによる天文学の改革
- 天体の動力学と運動霊
- ギルバートの重力理論
- ギルバートのケプラーへの影響
- ケプラーの動力学
- 磁石としての天体
- ケプラーの重力理論
第19章:一七世紀機械論哲学と力
- 機械論の品質証明
- ガリレイと重力
- デカルトの力学と重力
- デカルトの機械論と磁力
- ワルター・チャールトン
第20章:ロバート・ボイルとイギリスにおける機械論の変質
- フランシス・ベーコン
- トマス・ブラウン
- ヘンリー・パワーと「実験哲学」
- ロバート・ボイルの「粒子哲学」
- 機械論と「磁気発散気」
- 特殊的作用能力の容認
第21章:磁力と重力―フックとニュートン
- ジョン・ウィルキンズと磁気哲学
- ロバート・フックと機械論
- フックと重力--機械論からの離反
- 重力と磁力の測定
- フックと「世界の体系」
- ニュートンと重力
- 魔術の神聖化
- ニュートンと磁力
第22章:エピローグ―磁力法則の測定と確定
- ミュッセンブルークとヘルシャムの測定
- カランドリーニの測定
- ジョン・ミッシェルと逆二乗法則
- トビアス・マイヤーと渦動仮説の終焉
- マイヤーの磁気研究の方法
- マイヤーの論理--仮説・演繹過程
- クーロンによる逆二乗法則の確定
あとがき
注
文献
索引
第1巻
「遠隔力」の概念が、近代物理学の扉を開いた。古代ギリシャからニュートンとクーロンにいたる科学史空白の一千年余を解き明かす。西洋近代科学技術誕生の謎に真っ向からとりくんだ渾身の書き下ろし。第1巻は古代ギリシャ・ヘレニズム時代、ローマ帝国時代、中世キリスト教世界まで。
第1章:磁気学の始まり―古代ギリシャ
第2章:ヘレニズムの時代
第3章:ローマ帝国の時代
第4章:中世キリスト教世界
第5章:中世社会の転換と磁石の指向性の発見
第6章:トマス・アクィナスの磁力理解
第7章:ロジャー・ベーコンと磁力の伝播
第8章:ペトロス・ペレグリヌスと『磁気書簡』
第2巻
第2巻では、従来の力学史・電磁気学史でほとんど無視されてきたといっていいルネサンス期を探る。本書は技術者たちの技術にたいする実験的・合理的アプローチと、俗語による科学書執筆の意味を重視しつつ、思想の枠組としての魔術がはたした役割に最大の注目を払う。脱神秘化する魔術と理論化される技術。清新の気にみちた時代に、やがてふたつの流れは合流し、後期ルネサンスの魔術思想の変質―実験魔術―をへて、新しい科学の思想と方法を産み出すのである。
第9章:ニコラウス・クザーヌスと磁力の量化
第10章:古代の発見と前期ルネサンスの魔術
第11章:大航海時代と偏角の発見
第12章:ロバート・ノーマンと『新しい引力』
第13章:鉱業の発展と磁力の特異性
第14章:パラケルススと磁気治療
第15章:後期ルネサンスの魔術思想とその変貌
第16章:デッラ・ポルタの磁力研究
内容紹介:
第3巻でようやく近代科学の誕生に立ち会う。霊魂論・物活論の色彩を色濃く帯びたケプラーや、錬金術に耽っていたニュートン。重力理論を作りあげていったのは彼らであり、近代以降に生き残ったのはケプラー、ニュートン、クーロンの法則である。魔術的な遠隔力は数学的法則に捉えられ、合理化された。壮大な前科学史の終幕である。
2003年刊行、432ページ。
著者について:
山本義隆(やまもとよしたか)
1941年大阪生まれ。大阪府出身。大阪市立船場中学校、大阪府立大手前高等学校卒業。1964年、東京大学理学部物理学科卒業。 東京大学大学院博士課程中退。
1960年代、学生運動が盛んだったころに東大全共闘議長を務める。1969年の安田講堂事件前に警察の指名手配を受け地下に潜伏するが、同年9月の日比谷での全国全共闘連合結成大会の会場で警察当局に逮捕された。日大全共闘議長の秋田明大とともに、全共闘を象徴する存在であった。
学生時代より秀才でならし、大学では物理学科に進んで素粒子論を専攻した。大学院在学中には、京都大学の湯川秀樹研究室に国内留学しており、物理学者としての将来を嘱望されていたが、学生運動の後に大学を去り、大学での研究生活に戻ることはなかった。
その後は予備校教師に転じ、駿台予備学校では「東大物理」などのクラスに出講している。一方で科学史を研究しており、当初エルンスト・カッシーラーの優れた翻訳で知られたが、後に熱学・熱力学や力学など物理学を中心とした自然思想史の研究に従事し今日に至っている。遠隔力概念の発展史についての研究をまとめた『磁力と重力の発見』全3巻は、第1回パピルス賞、第57回毎日出版文化賞、第30回大佛次郎賞を受賞して読書界の話題となった。
山本義隆: ウィキペディアの記事 Amazonで著書を検索
理数系書籍のレビュー記事は本書で299冊目。
僕がこの本を読みたいと思ったきっかけは惑星の公転の原因が磁力だとケプラーが考えていたのを知ったことだった。チコ・ブラーエの20年におよぶ惑星の位置観測の記録から火星の公転が楕円軌道であることを導き、ケプラーの3法則を打ち立てた数学者ケプラーがなぜ磁力に公転運動の理由を求めたのか?太陽や惑星が磁石でできているとでも思っていたのだろうか?
磁力について正しい理解に達していなかった近代以前、磁力は「隠された力」であり「自然魔術」のひとつだった。一方で数学の手法を用い、もう一方で合理的な説明を放棄したとも見える磁力説を提唱していたことに違和感をもっていたのだ。
しかし「宇宙の神秘(1596)」、「新天文学(1609)」「宇宙の調和(1619)」というケプラー3部作の中で、彼は太陽系の惑星軌道半径が互いに内接する正多面体によって説明できるとか、惑星の公転運動によって奏でられる「メロディ」の研究を紹介している。それらにくらべれば磁力説はまだ許容できるものなのかもしれない。
著者の山本先生が本書を執筆を思い立ったのもまさに同じ理由だと「あとがき」にお書きになっている。近代に入ってもなお魔術思想は影響を残していた。しかし魔術思想は近代科学の誕生の足を引っ張っていたわけではなく、むしろ後押ししていたという意外な事実が本書を読むとわかる。
ケプラーに多大な影響を与えたウィリアム・ギルバートは著書『磁石論(1600)』によって地球が巨大な磁石であることを明確に示した。またコペルニクス、ケプラー、デカルト、ガリレイ、フック、ニュートンに至る過程でどのような発想の転換がおきていたか。イギリスの王立協会が設立される過程、原子仮説に基づく機械論による自然理解は17世紀にロバート・ボイルらによってどのように変化していったか。そしてその後クーロンらによって電気力と磁気力の測定されて両者がともに逆二乗法則に従って減衰していることが導かれ、近代の電磁気学が誕生するまでの経緯が詳細に解説されている。
本シリーズのタイトルは「磁力と重力の発見」であるが、重力はようやく第3巻で詳しく取り上げられる。アリストテレス哲学では宇宙の中心である地球の中心に戻ろうとする自然な運動として考えられていた重力は、どのような変遷をへて遠隔力としての重力に移行していったのか、そして早い段階で遠隔力であることが経験的に知られていた磁力は、原子仮説に基づく機械論の全盛期にどのように考えられていたのか。このあたりも本書を読んで得られる醍醐味のひとつである。
また天文学と物理学の区別が現代のスタイルに分かれていったのもこの時代である。ケプラー以前の天文学はコペルニクスの地動説の太陽系モデルも含めて「幾何学」だったからだ。天文学は日食や月食の予測、占星術、暦の作成をおこなえれば十分であり、天体間に働く力や運動はむしろ定性的な理解や哲学の範疇に属する「自然哲学」だった。ケプラー以降、天体間に働く力を関数であらわし数学を使って計算するようになり、力や運動という動力学の考え方が天文学の概念を近代的なものに変化させていった。天文学が単なる幾何学から物理学へ変化し始めたのである。
第2巻までは読むのが大変だったが、第3巻は行きつ戻りつはあるものの近代科学へ向かって比較的順調に進んでいくので好奇心が途切れずに読み通すことができた。ケプラーの洞察力の凄さに感動し、ガリレイやデカルト、ニュートンに対するイメージも若干修正された。そしてこれまでは「フックの法則」によってしか知らなかったロバート・フックがニュートンに与えた影響を知ったのも僕には初めてのことだった。
章立ては次のとおりだ。ヨーロッパ史だと西暦1600年頃から1800年頃まで。
第17章:ウィリアム・ギルバートの『磁石論』
第18章:磁気哲学とヨハネス・ケプラー
第19章:一七世紀機械論哲学と力
第20章:ロバート・ボイルとイギリスにおける機械論の変質
第21章:磁力と重力―フックとニュートン
第22章:エピローグ―磁力法則の測定と確定
第3巻の登場人物はとても多いので、主だった人物についてのみ年代順に、そして磁力と重力についての業績についてだけ紹介しておく。
ウィリアム・ギルバート(1544-1603)
著書『磁石論(1600)』によって次のことを述べた。
- 地球が巨大な磁石であることを提唱。
- 地球のレプリカとして球形磁石「テレラ(小地球)」を用いた磁力の実験を行った。
- 磁気哲学を提唱した。
- 検電器を発明し、琥珀現象(静電引力)の実験を行い、静電気研究の出発点を築いた。
- 彼の行った琥珀の実験は定性的なものにとどまっていた。
- 電気力は電気発散気と呼んだ物質による近接作用と考えた。
- 磁石にはその磁力がおよぶ「作用圏」があると考えた。
- 磁気の作用圏は実在的なものではなく、磁力は遠隔作用だと考えていた。
- 電気的な運動はおもに質料(materia)によって、磁気的な運動はおもに形相(forma)によって実現されると考えていた。
- 電気力の原因の質料は電気発散気という物質であり、磁力の原因の形相は非物質だと考えた。
- 地球が持つ磁力は地球自身の自転軸の方向を決め、さらに自転運動を引き起こすと考えた。その意味で彼はコペルニクスの地動説をいち早く取り入れていた。
- このように主張しつつも、地球を含むあらゆる天体は球であり、すべての球は創造主によって与えられた霊魂によって支配されて運動が決定づけられ、磁石さえも霊魂を持つと考えていた。
つまり地球は霊魂を有していることと磁性によりみずから回転し、みずからを方向づけるということは切り離して考えることができない。その2つをもってギルバートは地動説を受け入れることができたのである。
コルチェスターのウィリアム・ギルバートの著作、『磁石論』出版400周年を記念して
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/stern-j/demagint_j.htm
『磁石論』の英語版はここに公開されている。邦訳されている「磁石(および電気)論 新版」は150ページしかないので部分訳だ。
https://archive.org/details/williamgilbertc00wriggoog
ヨハネス・ケプラー(1571-1630)
「宇宙の神秘(1596)」、「新天文学(1609)」「宇宙の調和(1619)」というケプラー3部作によりケプラー3法則を提唱した。ケプラーはギルバートの『磁石論(1600)』を読んで多大な影響を受けていた。
コペルニクスの地動説の太陽系モデルでは惑星の軌道は真円である。コペルニクスにとって地球の公転軌道の中心はいわば「平均太陽」の位置である。軌道が楕円であることを確信していたケプラーは、楕円の中心(2つの焦点の中点)という何もない場所に「影響力」の中心があるはずがないことに気が付いていた。
ケプラーは惑星の公転運動の原因を当初は「運動霊」であるとしていたが、後に原因を磁力に求めた。それはギルバートの『磁石論(1600)』による影響である。ケプラーは太陽、惑星、月などの天体はすべて磁石であると考えていた。しかし磁力は引力として働くのではない。惑星に及んでいる太陽の磁力の作用圏は太陽が自転することによって回転し、地球を軌道の接線方向に引きずって公転運動を引き起こすと考えていた。また磁力が太陽から離れるに従って減衰することはギルバートの理論から知っていたが、作用圏を地球の公転面だけに限って考えたために逆一乗則に従って磁力が減衰するという理論だった。実際、彼は惑星の公転速度をもとに太陽の自転速度を3日だと割り出したが、もちろん見当はずれな値だ。
ケプラーの業績で見逃してはならないことは、磁力を起源とした誤った前提のもとに打ち立てられていたとはいえ幾何学に過ぎなかった惑星の運動の理論を動力学へ移行させたことにある。そして太陽が6個の惑星に及ぼす力、地球が月に及ぼす力、木星が4個の衛星に及ぼす力が同種類のものであることをもケプラーの法則は示唆していた。また静止した状態に限定されていたが「慣性(inertia)」という言葉を創ったのもケプラーである。これらのことが後にニュートンの万有引力発見へと結びついていく。
高校物理でケプラーの3法則は1~2ページで解説され、「ケプラーの法則の発見が物理学の根幹となる万有引力の法則の発見へとつなっていきます。」と簡潔に記述されている背後に、これほど壮大な想像力と深い洞察、精緻で厖大な計算があったことに僕は感動した。
邦訳された「宇宙の神秘(1596)」は376ページなのでなんとか読み切ったのだが、ケプラーの第1法則、第2法則を発表した「新天文学(1609)(目次情報)」と第3法則を発表した「宇宙の調和(1619)」はどちらも650ページ前後の大著で微積分誕生以前の数学手法、とりわけ三角比を複雑に組み合わせて用いる古代ギリシャのユークリッド幾何学で書かれた本である。僕はこの3冊を持っているが未読の2冊を読み解く自信はまったくない。
新天文学(ラテン語版)
https://www.kyoto-su.ac.jp/lib/kichosyo/kepler/pages/jk_001.html
宇宙の調和(英語版)
http://sacred-texts.com/astro/how/index.htm
ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)
ガリレイはみずから制作した望遠鏡を使って惑星の衛星の発見、太陽黒点や月面の観察をしたことにより、自然の見方や観測方法に根底的な変革をもたらした。
望遠鏡による太陽黒点や月面の凹凸は地上で観測される大地の起伏と同様に不規則で、天体を構成する物質も地上にある物質と同種のものであるというインスピレーションをもたらしたのだ。もともと神が創造した天体は天界という別世界にある完全な球であり、太陽黒点のようなしみや月面に凹凸などあるはずがないと考えられていたからだ。天体も物質であるのなら質量を持つのだろうという意味において、ニュートンの万有引力の発見に結びつくヒントになったといえよう。
ガリレイは地上の物体の運動法則、落体の法則を実験により導き、近代的な意味で世界最初の科学者と呼ばれている。そして彼の自然観は物質が無性質、不活性で受動的であるという機械論である。
しかしガリレイはケプラーの楕円軌道の意義を認めることができず、万有引力の発見を取り逃がした。遠隔力としての重力も受け入れることができなかった。ガリレイにとって太陽系は本質的に物理学の問題ではなかったのである。
またガリレイには力の概念が完全に欠落していて、その意味で彼の力学は動力学に到達せず数学的な運動学にとどまっていた。望遠鏡で惑星を観測していたものの、惑星の運動についての理論らしきものを何ひとつ作り出していない。天体力学という観念をとらえるのに完全に失敗していたのである。地動説という新しい宇宙像のために闘った殉教者のように言われているが、惑星運動のダイナミズムについては全く無知であったのだ。
本書で強調されているガリレイの業績とは、物体は「なぜ」落下するのかというそれまでの自然学の設問自体を退け、物体は「どのように」落下するのかという問題に守備範囲を限定し、事物や現象の数学的法則性を読み解く手法を創始したことである。そして仮説・論証・実験という近代科学の方法を編み出した。
ルネ・デカルト(1596-1650)
デカルトの自然観も機械論であるが、ガリレイの機械論とかなり異なっていた。彼は「感覚は認識を妨げかねない」ので実験的検証に頼らず演繹的論証のみを重視して自然を理解しようとした。彼は運動の第一原因として「神は宇宙の中につねに同量の運動を保存している」という命題を置き、そこから自然学の基本法則として次の3つの力学原理を導き出している。
第1法則:あらゆるものはできるだけ同じ状態を保とうとする。したがって一度動かされると、いつまでも動き続ける。
第2法則:すべての運動は、それ自身として直線的である。したがって円運動するものはその描く円の中心からつねに遠ざかろうとする。
第3法則:物体はより強力な他の物体と衝突するときには、自分の運動をなんら失わないが、より弱い物体と衝突するときにはその弱い物体に移しただけの運動を失う。
つまりデカルトは「慣性の法則」を初めて定式化し、「運動量の保存則」の萌芽形態を提唱したことで初期の力学理論の発展に大きな功績を残した。
しかし彼の力学は力の概念が欠如した衝突の理論に過ぎない。見かけの遠隔作用は空間に感覚ではとらえられない物質が存在するとし、惑星の運動についても太陽の回りを渦になって回転する微細物質が惑星を押しているからだと説明した。デカルトの「渦動仮説」である。この説の致命的な欠陥は、精密な観測に裏打ちされたケプラーの3法則を同じレベルの精密さで説明できないことにあった。
磁力については磁石や鉄には磁気粒子が通る通孔があり、磁気粒子の運動の結果生じるというあくまで機械論こだわった定性的な理解に留まっていた。
デカルトはコペルニクスの地動説を支持していたとはいえ、あくまで哲学者であり、数学者であったのだ。
ロバート・ボイル(1627-1691)
科学の世界でボイルを有名にしたのは、フックの協力で作り上げた真空ポンプをもちいた一連の大気と真空の実験と、現在「ボイルの法則」と呼ばれている事実の発表だった。彼の物質観は「粒子哲学」である。ボイルは引力を認めず、遠隔力としての引力は直接的接触による衝撃または圧力の結果であるとみなしていた。それゆえ遠隔力の典型である磁力も近接作用として説明されることになる。
ボイルにとって磁化とは純粋に機械的な作用であり、地球の磁力による磁気発散気が通孔をもつ鉄が影響を与えるというものだった。電気力についても電気物質による発散気に起源があるとした。
ロバート・フック(1635-1703)
「フックの法則」で有名なロバート・フックは、重力の原因が磁力であるかどうかを見極めるために、その減衰を数学関数であらわそうとしその関数形が等しければ両者は同じ原因によるものと考えた。彼はそのために重力と磁力が距離によりどのように減衰するかの実験を行った。実験はうまくいかなかったことは容易に想像できるが、魔術的な色彩に彩られていた磁力についての知が近代科学のものに大きく一歩近づいたのである。
またフックは惑星の運動は慣性による軌道接線方向への直線運動に中心物体からの引力による中心方向への加速(屈曲)が重ね合わされたものと考え、惑星運動を正しく解析する道を開いた。この点についてフックはニュートンに意見を求めたことがニュートンの惑星運動理論に大きな寄与をすることになった。
そしてフックは「世界の体系」が3つの仮説によて解明されると主張した。
1)太陽系のすべての天体の運動が距離をへだてて働く相互的な引力(中心力)に支配されていること。
2)すべての曲線運動が慣性運動からの逸れの結果であり、それをもたらす力が上記1)の引力であること。
3)その引力は距離とともに減少すること。そしてその力は逆二乗則に従って減少する。
これらはほとんどニュートンが導いた結論に等しいが、数学的に証明する手腕をフックは欠いていたのである。
フックがそのような境地に達していたことも、ニュートンと同時代を生きた人だということも僕は知らなかったのでまさに目から鱗が落ちる思いがした。
アイザック・ニュートン(1642-1727)
そのようなわけでフックが構想した「世界の体系」を込み入った円錐曲線の諸定理とデリケートな極限操作を駆使し、緻密で早大な数学的体系に仕上げたのがフックより7歳年下のニュートンである。ニュートンはケプラーの3法則から太陽と惑星のあいだに距離の二乗に反比例する引力が働いていることを導き出し、その引力が万有であると仮定し、惑星・衛星の運動ばかりか地球の形状から潮汐までその著書「プリンキピア(1687, 1713, 1726)」で説明してみせた。これは17世紀の素朴な機械論の制約を打ち破って、数理科学としての近代物理学を創始したという偉大な業績である。
以前僕は「万有引力(重力)の原因についてニュートンは理解していなかった。」と否定的な意味合いで紹介したことがあるが、本書を読んでむしろそれは見当違いであることがわかった。つまり、ニュートンは純粋に数学的な手法により万有引力のありようを示すことが自然哲学(物理学)の目的であり、万有引力の「原因」や「本質」、「存在理由」を問うことは目的ではなかったからだ。それらを意図的に排除していたのである。このように、かつてガリレイが運動学にたいしておこなっていた数学的現象主義の立場を、ニュートンは動力学まで押し広めたのである。
ニュートンが導いたのはケプラーの3法則から万有引力という「順問題」であり、万有引力からケプラーの3法則を導くという「逆問題」の導出には成功していなかったことは「古典力学の形成―ニュートンからラグランジュへ:山本義隆」という本に書かれている。「磁力と重力の発見」ではこのことについてふれられていなかった。
順問題の解法:
http://wakariyasui.sakura.ne.jp/p/mech/bannyuu/bannyuu.html
逆問題の解法(英語ページ):
http://galileo.phys.virginia.edu/classes/152.mf1i.spring02/KeplersLaws.htm
ニュートンが生涯に書き残したもののなかには、磁石や磁力について触れている箇所は散見されるが、主題として真正面から論じたものは見当たらない。
シャルル・ド・クーロン(1736-1806)
磁力の減衰がどのような法則に従っているかは、ミュッセンブルークとヘルシャム、カランドリーニ、ジョン・ミッシェル、トビアス・マイヤーなどによって測定、研究されてきたが、逆二乗則に従うことを最終的に導いたのはクーロンの測定によるものだった。クーロンは電気力の減衰が逆二乗則に従うことも測定で求めたことで有名だが、磁力の減衰の法則も彼の業績である。ともに「クーロンの法則」として知られている。磁力の減衰の測定が困難だったのは、磁石が単極でないこと、磁石が広がりをもった物体であることが理由である。測定の詳細は次のページをお読みになっていただきたい。
1777年~1787年:クーロンの法則
http://www.neomag.jp/mag_navi/history/history_08.php
このようにして瞬時に伝わる遠隔力として磁力と電気力、重力が理解されていったのだが、それらが光速で伝わる近接力であることがわかったのは、磁力と電気力については電磁気学と量子力学の完成、重力については一般相対性理論の完成を待たなければならなかった。しかし18世紀からみてそれははるか先の未来の理論である。
この「磁力と重力の発見」3部作をお書きになった後、山本先生は続編として「十六世紀文化革命」2部作、さらに「世界の見方の転換」3部作をお書きになり、「磁力と重力の発見」で語り尽くせなかったことを補っている。これらの本もいずれ読んでみたい。
ブログ記事で紹介できたのは本書のほんのハイライト部分に過ぎず、論理的につながらない箇所や抜けがたくさんでてくるのはやむをえない。記事では紹介できなかった社会的、思想的背景を含めてご理解いただくために、ぜひこの3部作に挑戦していただきたい。そして学校でケプラーの法則やニュートンの万有引力の法則を学ぶ高校生には「磁力と重力の発見」は難しすぎるので、せめて今回のブログ記事だけでも読んでほしいと僕は思うのだ。
「磁力と重力の発見〈1〉古代・中世:山本義隆」
「磁力と重力の発見〈2〉ルネサンス:山本義隆」
「磁力と重力の発見〈3〉近代の始まり:山本義隆」



関連ページ:
永久磁石の歴史と磁気科学の発展
http://www.neomag.jp/mag_navi/history/history_top.php
関連記事:
磁力と重力の発見〈1〉古代・中世:山本義隆
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/75ef1fc1216c255471fdbf65cc3a0c49
磁力と重力の発見〈2〉ルネサンス:山本義隆
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/16b61843d410a867f942f3f8aef13865
応援クリックをお願いします!




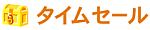
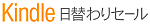
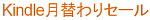
「磁力と重力の発見〈3〉近代の始まり:山本義隆」

第17章:ウィリアム・ギルバートの『磁石論』
- ギルバートとその時代
- 『磁石論』の位置と概要
- ギルバートと電気学の創設
- 電気力の「説明」
- 鉄と磁石と地球
- 磁気運動をめぐって
- 磁力の本質と球の形相
- 地球の運動と磁気哲学
- 磁石としての地球と霊魂
第18章:磁気哲学とヨハネス・ケプラー
- ケプラーの出発点
- ケプラーによる天文学の改革
- 天体の動力学と運動霊
- ギルバートの重力理論
- ギルバートのケプラーへの影響
- ケプラーの動力学
- 磁石としての天体
- ケプラーの重力理論
第19章:一七世紀機械論哲学と力
- 機械論の品質証明
- ガリレイと重力
- デカルトの力学と重力
- デカルトの機械論と磁力
- ワルター・チャールトン
第20章:ロバート・ボイルとイギリスにおける機械論の変質
- フランシス・ベーコン
- トマス・ブラウン
- ヘンリー・パワーと「実験哲学」
- ロバート・ボイルの「粒子哲学」
- 機械論と「磁気発散気」
- 特殊的作用能力の容認
第21章:磁力と重力―フックとニュートン
- ジョン・ウィルキンズと磁気哲学
- ロバート・フックと機械論
- フックと重力--機械論からの離反
- 重力と磁力の測定
- フックと「世界の体系」
- ニュートンと重力
- 魔術の神聖化
- ニュートンと磁力
第22章:エピローグ―磁力法則の測定と確定
- ミュッセンブルークとヘルシャムの測定
- カランドリーニの測定
- ジョン・ミッシェルと逆二乗法則
- トビアス・マイヤーと渦動仮説の終焉
- マイヤーの磁気研究の方法
- マイヤーの論理--仮説・演繹過程
- クーロンによる逆二乗法則の確定
あとがき
注
文献
索引
第1巻
「遠隔力」の概念が、近代物理学の扉を開いた。古代ギリシャからニュートンとクーロンにいたる科学史空白の一千年余を解き明かす。西洋近代科学技術誕生の謎に真っ向からとりくんだ渾身の書き下ろし。第1巻は古代ギリシャ・ヘレニズム時代、ローマ帝国時代、中世キリスト教世界まで。
第1章:磁気学の始まり―古代ギリシャ
第2章:ヘレニズムの時代
第3章:ローマ帝国の時代
第4章:中世キリスト教世界
第5章:中世社会の転換と磁石の指向性の発見
第6章:トマス・アクィナスの磁力理解
第7章:ロジャー・ベーコンと磁力の伝播
第8章:ペトロス・ペレグリヌスと『磁気書簡』
第2巻
第2巻では、従来の力学史・電磁気学史でほとんど無視されてきたといっていいルネサンス期を探る。本書は技術者たちの技術にたいする実験的・合理的アプローチと、俗語による科学書執筆の意味を重視しつつ、思想の枠組としての魔術がはたした役割に最大の注目を払う。脱神秘化する魔術と理論化される技術。清新の気にみちた時代に、やがてふたつの流れは合流し、後期ルネサンスの魔術思想の変質―実験魔術―をへて、新しい科学の思想と方法を産み出すのである。
第9章:ニコラウス・クザーヌスと磁力の量化
第10章:古代の発見と前期ルネサンスの魔術
第11章:大航海時代と偏角の発見
第12章:ロバート・ノーマンと『新しい引力』
第13章:鉱業の発展と磁力の特異性
第14章:パラケルススと磁気治療
第15章:後期ルネサンスの魔術思想とその変貌
第16章:デッラ・ポルタの磁力研究