「マイ・コンピュータ入門―コンピュータはあなたにもつくれる:安田寿明」
内容:
もはや、コンピュータがガラス張りの部屋に置かれ、ひとにぎりのエリート・ビジネスマンやエンジニアだけがそれを操作する時代は終わった。
神様扱いされたコンピュータは死に、だれもが気軽に使え、持つことができる新しいコンピュータ時代がやってきたのである。そして、その新型コンピュータ―マイ・コンピュータは、中学生でも、その気になれば、自作できるようになったのである。
さて、コンピュータを手づくりする人たちまで出現したいま、これからの私たちの前にどのようなコンピュータ文化が展開されていくのだろうか?
著者略歴(1977年、本書出版当時の情報)
安田寿明(やすだ・としあき):昭和10年、兵庫県に生まれる。昭和34年、電気通信大学経営工学科卒業後、読売新聞社に勤務。編集局社会部員、米国特派員、社長直属総合計画室員などを経て、昭和45年退社。現在東京電機大学工学部電気通信工学科助教授。『知識産業』(ダイヤモンド社)などのほか、情報産業、漢字情報処理システム、有線テレビジョンに関する著書、論文が多数ある。
理数系書籍のレビュー記事は本書で225冊目。(マイコンは電子工学系だけど広い意味で理系としておく。)
1976年にマイコンキットが登場する4年も前から、自分用のコンピュータを6台も作り上げた著者によるマイコン入門の書。この本によって多くの人がマイコンによって何ができるのかを正しく理解するようになった。未来への夢が生き生きと語られている安田寿明先生が42歳のときにお書きになった「マイ・コンピュータ3部作」の1冊目のレビュー記事。
章立てと大まかな内容は次のとおり。(詳細な目次は記事のいちばん下に書いておいた。)
第1章:“神”ではなくなったコンピュータ
1977年の春、秋葉原に突如コンピュータ・ショップが出現したことが驚きをもって紹介される。これまでコンピュータは会社や大学でしか使われていず、一般の人にとっては“神”のように神秘的で万能な力を持った存在だった。ところがマイコンキットがお小遣い程度の値段で売られるようになり、個人がコンピュータを持つことができる時代が始まったのだ。
第2章:マイ・コンピュータが生まれるまで
マイコンの心臓部はCPUだ。世界最初のCPUが開発されるまでのアメリカ、日本の電子産業の様子が紹介される。日本の零細企業ビジコン社、アメリカでもその当時は零細企業だったインテル社がどのように結びつき、CPUが現実のものになっていったかが生々しく語られる。日本に初出荷されたIntel 8008の試作品は20個あったが、1972年4月に著者はそのうちの1個を8万5千円で購入。半年後その価格は4万5千円になり、5年後には2千円にまで価格が下がった。マイコンをめぐってメーカーの間で激しい競争が行われることになったが、これまでとは全く違う新しいタイプのコンピュータ出現によって大メーカーから中小企業まで「全産業総アマチュア化」の時代をむかえることになった。
横浜まで出向いて購入したIntel 8008をもとに周辺回路を自ら設計し、著者はマイ・コンピュータ第1号を完成させる。それ以前に購入して修理したミニコンも含めて1976年にNEC TK-80が発売されるまでに著者は6台のコンピュータを自作することになる。
第1号機の写真(出力は8個のLED電球で表示されていた。写真はクリックで拡大する。)
クリックで拡大
![]()
第3章:マイ・コンピュータのつくりかた
アメリカではもともとマイコンキット発売以前から、個人でコンピュータを所有している人が何人もいた。それは企業にレンタルされていたミニコンやオフコンが減価償却期間を過ぎ、そのようなコンピュータをキロやトンなど重さ単位で売買する中古市場があったからだ。コンピュータを買ったアマチュアたちはお互いに技術情報を交換し、いくつかのアマチュア・コンピュータ・クラブが生まれた。それと同じ状況が日本でも少し遅れておこり、著者はミニコンを1台購入することになる。マイコンが誕生する前、日本やアメリカにはそのような状況があったのだ。アマチュアによるモノづくりという点では日本人よりアメリカ人のほうが進んでいた。もともとコンピュータだけでなくあらゆる物について「DIY(=Do It Yourself)」のキットを好む国民性があったからだ。日本ではNEC TK-80が発売されるやいなや、各社が競ってマイコンキットを発売することになった。
第4章:電子音楽への応用
マイ・コンピュータ本体だけではほとんど何も役に立たない。著者は娘さんのために買った中古のエレクトーンを自動演奏させることに挑戦する。鍵盤のひとつひとつにリレーを取り付けマイコンからの司令で鍵盤を操作するのだ。その後、このシステムはさまざまな楽器の音を生成して奏でるシンセサイザーに進化する。シンセサイザーによる音楽は冨田勲が当時から知られていたが、シンセサイザーとコンピュータをつなげることでコンピュータ音楽の世界は新たなフェーズへと発展することが生き生きと語られる。
第5章:マイ・コンピュータの拡張システム
マイ・コンピュータと周辺機器を接続するためには「インタフェース回路」が必要なこと、利用可能な周辺機器などについて解説する。文字出力にはテレタイプライターがあったが、当時は75万円もした。より安価な出力装置としてテレビ受像機が利用できることが紹介される。また著者は自前の6台のコンピュータどうしを接続し、家庭内にコンピュータ・センターを構築する。
データ通信については当時から電電公社(現在のNTT)によるTSS(タイム・シェアリング・サービス)があったが、料金が高すぎて著者の安月給ではとても使えない。幸い通常のアマチュア無線免許のほかに著者は宇宙通信(衛星を使った通信)の免許も持っていたので、この回線を使って自らTSSシステムを構築して海外の利用者に対して計算サービスを提供することを思いつく。そしてそれを実行に移していこうとするわけだが。。。
第6章:テクノ・クラフト・アートの時代
マイ・コンピュータ技術によって社会や仕事がどのように変わっていくかが解説される。専門分業化が進み、徹底した工業化社会が生まれることになるのだ。その中でひとりの個人に必要とされる知識は限定されることになる。自分に必要な勉強をするだけでよいのか?それとも自分の生きがいのために幅広く勉強すべきなのか?そのようなことを著者は問いかける。
日本でも自作ブームが始まり、半田ごてを手にする人が増えてきた。またビデオ・ゲームの完成品も売られるようになり、カラー化されたビデオ・ゲームがでてくるのも時間の問題だと著者は予言する。マイ・コンピュータが身の回りのあらゆる物に組み込まれる時代はすぐそこにあり、今が「テレネトニクスのあけぼの」であり、新たな変化の時代をむかえているのだ。
僕が本書を読んだのは中学3年のときだが、興奮して夜も眠れなかったことを覚えている。マイ・コンピュータに奮闘する安田先生の姿や周辺機器がつぎつぎにつなげられてコンピュータが成長していくことに「無限の可能性」を空想しながら読んでいた。当時は耳慣れない専門用語や回路図もていねいに解説されているので中学生でもじゅうぶん理解できる本だ。
36年経った今、あらためて読みなおしてみると、当時の安田先生の安月給サラリーマンとしてのお姿、月曜から土曜は本業のお仕事に時間をとられ、土曜の深夜から日曜にかけて趣味のコンピュータ作りに没頭するお姿、マイ・コンピュータを安く仕上げるためにどのような戦略をとられていたか、奥様や娘さんにどのような思いを持たれていたか、奥様や娘さんからどのように思われていたかなど昔とはまた違う部分を楽しむことができた。
さらにマイコン登場以前のコンピュータの中古市場、DIYキットに対する日米のアマチュア文化の違いについての説明は特に興味深かった。当時のミニコンやオフコンの機能や性能のことを今では「IPSJコンピュータ博物館」などのページを通じて知ることができるだけに、それをアマチュアが「いじっていた」ことにとても驚かされたからだ。
本書が日本のアマチュアの人たちに与えた影響はとても大きい。この本に出会ってコンピュータ開発者、技術者への道を選択した人はきっと多かったことだろう。
「マイ・コンピュータ入門―コンピュータはあなたにもつくれる:安田寿明」(リンク2)
「マイ・コンピュータをつくる―組み立てのテクニック:安田寿明」(リンク2)
「マイコンピュータをつかう―周辺機器と活用の実際:安田寿明」
![]()
![]()
![]()
関連記事:
安田寿明先生の「マイ・コンピュータ」3部作(ブルーバックス)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e54e4eb38380ff2ff2f51747ca7b4f75
NEC TK-80やワンボードマイコンのこと
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/36db2417701c58efa1ac81343e70227b
真空管式コンピュータへのノスタルジア(EDSAC)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/14c9aeedfcda78c9fd9ff4b677435283
ファインマン計算機科学:ファインマン, A.ヘイ, R.アレン
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/4f7f453019fd463ed2bfdeaa7b288d79
量子コンピュータ入門:宮野健次郎、古澤明
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ef75709187cf4b35a12f2d9fdf73a320
応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。
![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()
![人気ブログランキングへ]()
![]()
![]()
「マイ・コンピュータ入門―コンピュータはあなたにもつくれる:安田寿明」
![]()
第1章:“神”ではなくなったコンピュータ
- コンピュータ・バーゲン・ショップの出現
- ICBMにもまさる強力兵器!
- デルファイ神殿かコンピュータか
- “神”は死んだ!マイコンが生まれた!
第2章:マイ・コンピュータが生まれるまで
- トラは死して皮を残す
- “白紙”の本を作ろう
- 全産業、アマチュア化の時代へ
- 財布、はたいてマイ・コンピュータ
- がんばれ!四畳半メーカー
- マイ・コンピュータの内部
- マイ・コンピュータの本体システム
- LSIの内部
- トランジスタから集積回路(IC)へ
- TTLからMOS・LSIへ
- LSIから超LSIへ
第3章:マイ・コンピュータのつくりかた
- 「つくる」ということ
- アマチュア・コンピュータ・クラブの誕生
- 家族ぐるみのコンピュータ・ショウ
- 日本にも中古コンピュータ市場が
- 赤坂、六本木よりもコンピュータを
- DIYキットの出現
- マイコン・キットの社会経済ダイナミックス
- 無念や残念!動かないコンピュータ
- 日本電気、東芝もキット戦線へ
- 男性諸君、台所へ突進せよ!
- 製作開始にさきだって
- ハダカでもあぶない?MOS・LSI
第4章:電子音楽への応用
- 電子オルガンを自動演奏する
- 中古エレクトーンの改造の記
- 実践的電子楽器マスター法
- リリー・マルレーンとエレクトーン
- 音階鍵盤に番地を割り当てる
- ドは「C」、レは「D」、「G」はソ
- ミュージック・シンセサイザーへのエスカレート
- ビートルズもまっさお!グループ・サウンズ「コンピューターズ」
- コンピュータ自身を電子オルガンに
- まさに千手観音、コンピュータ楽器
- ひとり楽しむ「DEN状況」
第5章:マイ・コンピュータの拡張システム
- 整合の技術--インタフェース
- インタフェースの実際
- テレタイプライター接続の基本
- テレビ受像機を活用しよう
- 高くつくデータ通信
- マイ・ホーム・コンピュータ・センター
- 壮大なオンライン・システム
- ステレオ・システムも総動員
- ああ堂々の宇宙通信地球局
- 通信衛星も手づくりで
- コンピュータは単なる人間の代行機械
第6章:テクノ・クラフト・アートの時代
- 専門分業化徹底の工業化社会
- 仕事のための勉強?生きがいのための勉強?
- DIYの静かなるブーム
- “聖域”をおかすべからず
- 機械をおそれることなかれ!
- ハンダゴテよ、こんにちは
- 広がる手づくりブーム
- ビデオ・ゲームの出現
- カラー・グラフィック・ディスプレイも
- 電子ミシンとマイ・コンピュータ
- 天才エンジニアへの墓碑銘
- 中小企業のしかばねを乗りこえて
- テレネトニクスのあけぼの
あとがきにかえて
- シンクタンクYRI見習い技手の物語
内容:
もはや、コンピュータがガラス張りの部屋に置かれ、ひとにぎりのエリート・ビジネスマンやエンジニアだけがそれを操作する時代は終わった。
神様扱いされたコンピュータは死に、だれもが気軽に使え、持つことができる新しいコンピュータ時代がやってきたのである。そして、その新型コンピュータ―マイ・コンピュータは、中学生でも、その気になれば、自作できるようになったのである。
さて、コンピュータを手づくりする人たちまで出現したいま、これからの私たちの前にどのようなコンピュータ文化が展開されていくのだろうか?
著者略歴(1977年、本書出版当時の情報)
安田寿明(やすだ・としあき):昭和10年、兵庫県に生まれる。昭和34年、電気通信大学経営工学科卒業後、読売新聞社に勤務。編集局社会部員、米国特派員、社長直属総合計画室員などを経て、昭和45年退社。現在東京電機大学工学部電気通信工学科助教授。『知識産業』(ダイヤモンド社)などのほか、情報産業、漢字情報処理システム、有線テレビジョンに関する著書、論文が多数ある。
理数系書籍のレビュー記事は本書で225冊目。(マイコンは電子工学系だけど広い意味で理系としておく。)
1976年にマイコンキットが登場する4年も前から、自分用のコンピュータを6台も作り上げた著者によるマイコン入門の書。この本によって多くの人がマイコンによって何ができるのかを正しく理解するようになった。未来への夢が生き生きと語られている安田寿明先生が42歳のときにお書きになった「マイ・コンピュータ3部作」の1冊目のレビュー記事。
章立てと大まかな内容は次のとおり。(詳細な目次は記事のいちばん下に書いておいた。)
第1章:“神”ではなくなったコンピュータ
1977年の春、秋葉原に突如コンピュータ・ショップが出現したことが驚きをもって紹介される。これまでコンピュータは会社や大学でしか使われていず、一般の人にとっては“神”のように神秘的で万能な力を持った存在だった。ところがマイコンキットがお小遣い程度の値段で売られるようになり、個人がコンピュータを持つことができる時代が始まったのだ。
第2章:マイ・コンピュータが生まれるまで
マイコンの心臓部はCPUだ。世界最初のCPUが開発されるまでのアメリカ、日本の電子産業の様子が紹介される。日本の零細企業ビジコン社、アメリカでもその当時は零細企業だったインテル社がどのように結びつき、CPUが現実のものになっていったかが生々しく語られる。日本に初出荷されたIntel 8008の試作品は20個あったが、1972年4月に著者はそのうちの1個を8万5千円で購入。半年後その価格は4万5千円になり、5年後には2千円にまで価格が下がった。マイコンをめぐってメーカーの間で激しい競争が行われることになったが、これまでとは全く違う新しいタイプのコンピュータ出現によって大メーカーから中小企業まで「全産業総アマチュア化」の時代をむかえることになった。
横浜まで出向いて購入したIntel 8008をもとに周辺回路を自ら設計し、著者はマイ・コンピュータ第1号を完成させる。それ以前に購入して修理したミニコンも含めて1976年にNEC TK-80が発売されるまでに著者は6台のコンピュータを自作することになる。
第1号機の写真(出力は8個のLED電球で表示されていた。写真はクリックで拡大する。)
クリックで拡大

第3章:マイ・コンピュータのつくりかた
アメリカではもともとマイコンキット発売以前から、個人でコンピュータを所有している人が何人もいた。それは企業にレンタルされていたミニコンやオフコンが減価償却期間を過ぎ、そのようなコンピュータをキロやトンなど重さ単位で売買する中古市場があったからだ。コンピュータを買ったアマチュアたちはお互いに技術情報を交換し、いくつかのアマチュア・コンピュータ・クラブが生まれた。それと同じ状況が日本でも少し遅れておこり、著者はミニコンを1台購入することになる。マイコンが誕生する前、日本やアメリカにはそのような状況があったのだ。アマチュアによるモノづくりという点では日本人よりアメリカ人のほうが進んでいた。もともとコンピュータだけでなくあらゆる物について「DIY(=Do It Yourself)」のキットを好む国民性があったからだ。日本ではNEC TK-80が発売されるやいなや、各社が競ってマイコンキットを発売することになった。
第4章:電子音楽への応用
マイ・コンピュータ本体だけではほとんど何も役に立たない。著者は娘さんのために買った中古のエレクトーンを自動演奏させることに挑戦する。鍵盤のひとつひとつにリレーを取り付けマイコンからの司令で鍵盤を操作するのだ。その後、このシステムはさまざまな楽器の音を生成して奏でるシンセサイザーに進化する。シンセサイザーによる音楽は冨田勲が当時から知られていたが、シンセサイザーとコンピュータをつなげることでコンピュータ音楽の世界は新たなフェーズへと発展することが生き生きと語られる。
第5章:マイ・コンピュータの拡張システム
マイ・コンピュータと周辺機器を接続するためには「インタフェース回路」が必要なこと、利用可能な周辺機器などについて解説する。文字出力にはテレタイプライターがあったが、当時は75万円もした。より安価な出力装置としてテレビ受像機が利用できることが紹介される。また著者は自前の6台のコンピュータどうしを接続し、家庭内にコンピュータ・センターを構築する。
データ通信については当時から電電公社(現在のNTT)によるTSS(タイム・シェアリング・サービス)があったが、料金が高すぎて著者の安月給ではとても使えない。幸い通常のアマチュア無線免許のほかに著者は宇宙通信(衛星を使った通信)の免許も持っていたので、この回線を使って自らTSSシステムを構築して海外の利用者に対して計算サービスを提供することを思いつく。そしてそれを実行に移していこうとするわけだが。。。
第6章:テクノ・クラフト・アートの時代
マイ・コンピュータ技術によって社会や仕事がどのように変わっていくかが解説される。専門分業化が進み、徹底した工業化社会が生まれることになるのだ。その中でひとりの個人に必要とされる知識は限定されることになる。自分に必要な勉強をするだけでよいのか?それとも自分の生きがいのために幅広く勉強すべきなのか?そのようなことを著者は問いかける。
日本でも自作ブームが始まり、半田ごてを手にする人が増えてきた。またビデオ・ゲームの完成品も売られるようになり、カラー化されたビデオ・ゲームがでてくるのも時間の問題だと著者は予言する。マイ・コンピュータが身の回りのあらゆる物に組み込まれる時代はすぐそこにあり、今が「テレネトニクスのあけぼの」であり、新たな変化の時代をむかえているのだ。
僕が本書を読んだのは中学3年のときだが、興奮して夜も眠れなかったことを覚えている。マイ・コンピュータに奮闘する安田先生の姿や周辺機器がつぎつぎにつなげられてコンピュータが成長していくことに「無限の可能性」を空想しながら読んでいた。当時は耳慣れない専門用語や回路図もていねいに解説されているので中学生でもじゅうぶん理解できる本だ。
36年経った今、あらためて読みなおしてみると、当時の安田先生の安月給サラリーマンとしてのお姿、月曜から土曜は本業のお仕事に時間をとられ、土曜の深夜から日曜にかけて趣味のコンピュータ作りに没頭するお姿、マイ・コンピュータを安く仕上げるためにどのような戦略をとられていたか、奥様や娘さんにどのような思いを持たれていたか、奥様や娘さんからどのように思われていたかなど昔とはまた違う部分を楽しむことができた。
さらにマイコン登場以前のコンピュータの中古市場、DIYキットに対する日米のアマチュア文化の違いについての説明は特に興味深かった。当時のミニコンやオフコンの機能や性能のことを今では「IPSJコンピュータ博物館」などのページを通じて知ることができるだけに、それをアマチュアが「いじっていた」ことにとても驚かされたからだ。
本書が日本のアマチュアの人たちに与えた影響はとても大きい。この本に出会ってコンピュータ開発者、技術者への道を選択した人はきっと多かったことだろう。
「マイ・コンピュータ入門―コンピュータはあなたにもつくれる:安田寿明」(リンク2)
「マイ・コンピュータをつくる―組み立てのテクニック:安田寿明」(リンク2)
「マイコンピュータをつかう―周辺機器と活用の実際:安田寿明」


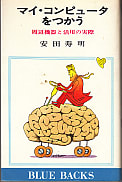
関連記事:
安田寿明先生の「マイ・コンピュータ」3部作(ブルーバックス)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e54e4eb38380ff2ff2f51747ca7b4f75
NEC TK-80やワンボードマイコンのこと
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/36db2417701c58efa1ac81343e70227b
真空管式コンピュータへのノスタルジア(EDSAC)
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/14c9aeedfcda78c9fd9ff4b677435283
ファインマン計算機科学:ファインマン, A.ヘイ, R.アレン
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/4f7f453019fd463ed2bfdeaa7b288d79
量子コンピュータ入門:宮野健次郎、古澤明
http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ef75709187cf4b35a12f2d9fdf73a320
応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。




「マイ・コンピュータ入門―コンピュータはあなたにもつくれる:安田寿明」

第1章:“神”ではなくなったコンピュータ
- コンピュータ・バーゲン・ショップの出現
- ICBMにもまさる強力兵器!
- デルファイ神殿かコンピュータか
- “神”は死んだ!マイコンが生まれた!
第2章:マイ・コンピュータが生まれるまで
- トラは死して皮を残す
- “白紙”の本を作ろう
- 全産業、アマチュア化の時代へ
- 財布、はたいてマイ・コンピュータ
- がんばれ!四畳半メーカー
- マイ・コンピュータの内部
- マイ・コンピュータの本体システム
- LSIの内部
- トランジスタから集積回路(IC)へ
- TTLからMOS・LSIへ
- LSIから超LSIへ
第3章:マイ・コンピュータのつくりかた
- 「つくる」ということ
- アマチュア・コンピュータ・クラブの誕生
- 家族ぐるみのコンピュータ・ショウ
- 日本にも中古コンピュータ市場が
- 赤坂、六本木よりもコンピュータを
- DIYキットの出現
- マイコン・キットの社会経済ダイナミックス
- 無念や残念!動かないコンピュータ
- 日本電気、東芝もキット戦線へ
- 男性諸君、台所へ突進せよ!
- 製作開始にさきだって
- ハダカでもあぶない?MOS・LSI
第4章:電子音楽への応用
- 電子オルガンを自動演奏する
- 中古エレクトーンの改造の記
- 実践的電子楽器マスター法
- リリー・マルレーンとエレクトーン
- 音階鍵盤に番地を割り当てる
- ドは「C」、レは「D」、「G」はソ
- ミュージック・シンセサイザーへのエスカレート
- ビートルズもまっさお!グループ・サウンズ「コンピューターズ」
- コンピュータ自身を電子オルガンに
- まさに千手観音、コンピュータ楽器
- ひとり楽しむ「DEN状況」
第5章:マイ・コンピュータの拡張システム
- 整合の技術--インタフェース
- インタフェースの実際
- テレタイプライター接続の基本
- テレビ受像機を活用しよう
- 高くつくデータ通信
- マイ・ホーム・コンピュータ・センター
- 壮大なオンライン・システム
- ステレオ・システムも総動員
- ああ堂々の宇宙通信地球局
- 通信衛星も手づくりで
- コンピュータは単なる人間の代行機械
第6章:テクノ・クラフト・アートの時代
- 専門分業化徹底の工業化社会
- 仕事のための勉強?生きがいのための勉強?
- DIYの静かなるブーム
- “聖域”をおかすべからず
- 機械をおそれることなかれ!
- ハンダゴテよ、こんにちは
- 広がる手づくりブーム
- ビデオ・ゲームの出現
- カラー・グラフィック・ディスプレイも
- 電子ミシンとマイ・コンピュータ
- 天才エンジニアへの墓碑銘
- 中小企業のしかばねを乗りこえて
- テレネトニクスのあけぼの
あとがきにかえて
- シンクタンクYRI見習い技手の物語